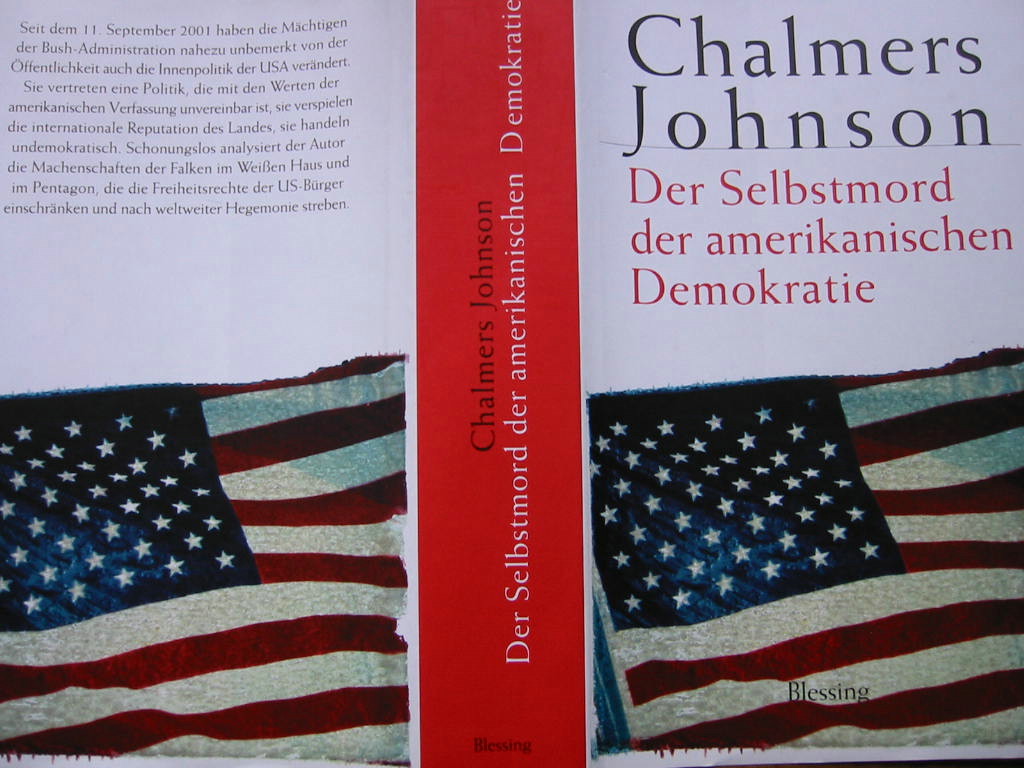映画「戦争のはじめかた」の「おわりかた」 2005年5月9日
今年の1月、会議の合間に有楽町で半年ぶりに映画をみた。「戦争のはじめかた」。あと数日で上映終了。これを逃すとすぐには上映されそうもないマイナーな映画である。だめもとで上映時間を手帳にメモしておいたので、一瞬の決断で足が地下鉄に向いていた。
 この作品は2001年9月のカナダ・トロント国際映画祭で、会場を騒然とさせた。そして、全米で上映されようとしたまさにそのときに「9.11」が起きて、あえなくお蔵入りとなった。アフガン戦争、イラク戦争と続いて、全米公開が5度も延期になった。館内で購入したパンフレットには、「不謹慎なつくりごと」ではなく「真実がここにある」とある。米軍基地内部の話なのに、英・独合作(2001年)である点も面白い。「愛国心」を強調する米国の場合、自国軍隊の矛盾や腐敗をここまで徹底して暴き、コケにするのは難しいかもしれない。
この作品は2001年9月のカナダ・トロント国際映画祭で、会場を騒然とさせた。そして、全米で上映されようとしたまさにそのときに「9.11」が起きて、あえなくお蔵入りとなった。アフガン戦争、イラク戦争と続いて、全米公開が5度も延期になった。館内で購入したパンフレットには、「不謹慎なつくりごと」ではなく「真実がここにある」とある。米軍基地内部の話なのに、英・独合作(2001年)である点も面白い。「愛国心」を強調する米国の場合、自国軍隊の矛盾や腐敗をここまで徹底して暴き、コケにするのは難しいかもしれない。
ストーリーはいたって単純である。1989年10月(「ベルリンの壁」崩壊の1カ月前)。場所は旧西ドイツ・シュトゥットガルトにある米軍基地。戦う敵がいない兵士たちは、あり余るほどの暇をもて余している。映画はその「退屈な日常」を、怠惰で退廃的な空気のなかで描いていく。物資の横流し、いじめと暴力、人種差別、ヘロイン密造などやりたり放題である。無教養な兵士。「俺たちはどっちのドイツにいるんだ」と一人が問うと、別の兵士が「東じゃねぇのか」なんてやっている。ヘロイン作りの待ち時間に雑談する彼らの側で、テレビが今まさに「ベルリンの壁」が崩壊するニュースを放映しているのに、誰も気にかけない。世の中のことにはまったく関心がなく、無意味な軍務や訓練の合間に(否、任務遂行中ですら)、自己の欲望のおもむくままに生きている。巨大な軍隊にとって「最大の敵」は、実は「何もすることがない」ということらしい。そのことがわかってしまわないよう、たくさんの「任務」が存在する。海外駐留米軍、もっといえば「外征軍」の無意味さが、単なる士気低下にとどまらない、人間や組織の頽廃にまで及んでいるさまを、ブラックな手法で描いている。作品の終わり近くに出てくるニーチェの言葉は痛烈である。「平和な時、戦争は自ら戦争する」と。秋山登氏の読み解きでは、「戦争は軍隊の生理で、戦時も平時も存在しない、ということ」になる(パンフ9頁)。
作品の質という点では、おすすめの名作というわけではない。何か明るい展望が見えるわけでもなければ、主人公に感情移入できるわけでもない。だが、軍隊の病理と生理を、ジトジトした暗さや声高な反戦メッセージで訴えかけるのではなく、どこか居直ったというか、突き抜けた明るさとユーモアで描いた作品というのも珍しい。この明るい「毒」は貴重である。加えて、この映画の一番の注目点は、軍隊が一切協力しない映画なのに、戦車や軍用車両、軍服から軍用品まで大量に登場することだ。そのほとんどを民間のマニアやコレクターから借りて撮影したというから驚く。ヨーロッパの「軍事おたく」はスケールが違うと思った。砲塔やサイドスカートの形などから、明らかに米軍のM60戦車ではなく、ドイツ軍のレオパルドⅠ型戦車であることはすぐわかるのだが、それでも本物の戦車を個人コレクターから借りて撮影できるというのはすごい。軍服400着も、地元コレクターの提供という。そして、この映画の「おわりかた」も意味深長である。だが、ネタバレになるので、映画紹介のルールとしてここでは触れないでおこう。ともあれ、軍隊を徹底してコケにする、米軍・ドイツ連邦軍の全面的非協力の「反軍映画」は痛快だった。
映画をみながら思い出したのが、チャルマーズ・ジョンソン(カリフォルニア大学名誉教授、元CIA顧問)の指摘である。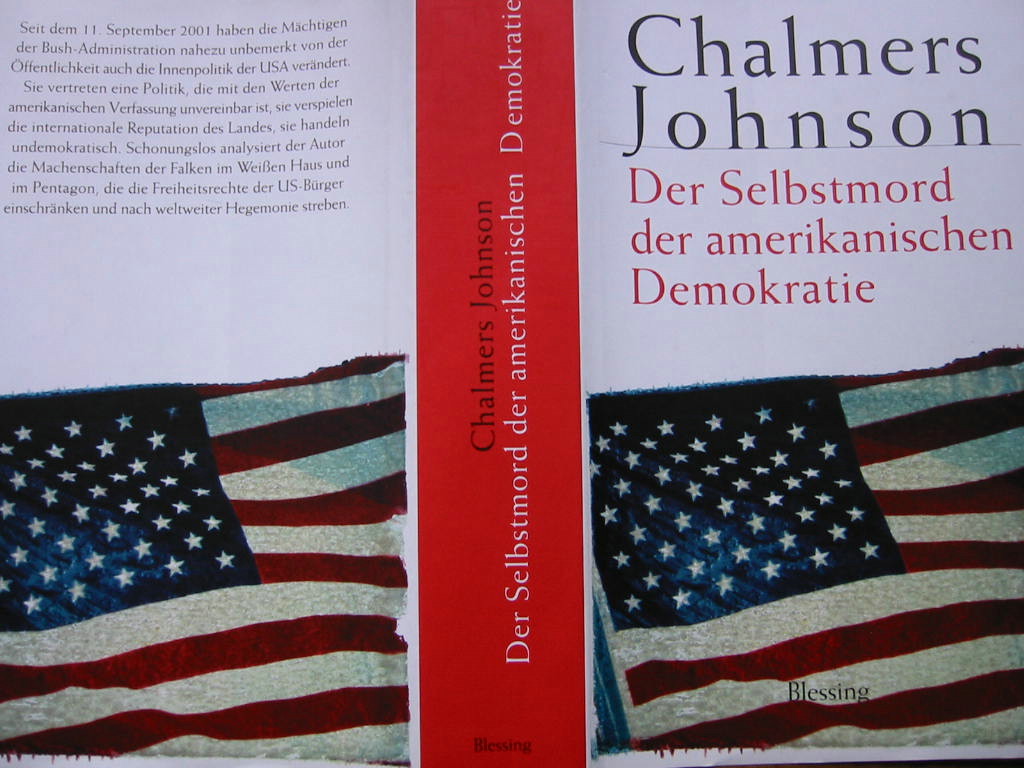 『アメリカ民主主義の自殺』(Chalmers Johnson, Der Selbstmord der amerikanischen Demokratie, 2003)など数冊を昨年読んで、「直言」でも簡単に紹介したことがある。ジョンソンは沖縄に滞在したこともある。彼の問題意識は実に明快。危機や脅威に対処するために米軍が展開し、軍事基地が必要になるのではない。米軍にとって快適な居住条件のある基地を必要とするから、米軍の世界展開があり、危機や脅威が「作られていく」のである。東京の都心にもリゾートホテルをもち、全世界に234の米軍専用ゴルフ場をもつためには、危機や脅威がなくなっては困るわけだ。なぜ米軍は沖縄を手放さないか。ジョンソンはいう。「その答えは明白だ。旧ソ連の軍隊が東ドイツ駐留を楽しんだのと同じ理由から、アメリカ軍も沖縄駐留を楽しんでいるのである。自国の軍事植民地における生活は、ソ連の軍人にとってもアメリカの軍人にとっても、母国ではほとんど望めないほどすばらしいものなのだ」。沖縄は「ペンタゴンの軍事植民地」であり、軍人とその家族にとって、「アメリカでは決して体験できないことを体験できる巨大な隠れ家なのだ」という(『アメリカ帝国への報復』集英社)。この快適な「植民地」を維持するために、脅威や危機はいくらでも作れるわけだ。だか、そんな「自己チュー」に付き合わされる方はたまったものではない。米軍のトランスフォーメーションのなかで、米陸軍第1軍団司令部が座間に進出する計画だが、第1軍団の任務は米国が「不安定な弧」と勝手に決めつけたアジア・中東地域を、軍事的に管理・統制することである。この米軍戦略の展開に応じて、この地域における新たな紛争が「紛争らしく」顕在化してくるだろう。マスコミがまたそれをセンセーショナルに伝え、米軍の「仕事」が確保されていく。日米安保条約6条(極東条項)に基づく基地使用条件は、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」であるが、第1軍団司令部が担任するであろう「不安定な弧」は「極東」よりはるかに広大な地域である。当然、この極東条項との抵触が危惧されるところである。そこで最近、米側は第1軍団司令部の作戦指揮を極東地域に限定するかのような態度をとりはじめている(『東京新聞』4月7日付)。日本の国内世論向けの説明であることは明らかであり、そのまま信じることはできない。この夏にも「新・新日米安保共同宣言」が予定されている(『読売新聞』1月14日付「スクープ」〔先触れ〕記事参照)。1996年の「新日米安保共同宣言」が「アジア・太平洋地域の安定」を日米の「死活的利益」にカウントしたが、2005年の「新・新日米安保共同宣言」は、日米安保体制が「グローバル安保体制」に転換する契機となるだろう。
『アメリカ民主主義の自殺』(Chalmers Johnson, Der Selbstmord der amerikanischen Demokratie, 2003)など数冊を昨年読んで、「直言」でも簡単に紹介したことがある。ジョンソンは沖縄に滞在したこともある。彼の問題意識は実に明快。危機や脅威に対処するために米軍が展開し、軍事基地が必要になるのではない。米軍にとって快適な居住条件のある基地を必要とするから、米軍の世界展開があり、危機や脅威が「作られていく」のである。東京の都心にもリゾートホテルをもち、全世界に234の米軍専用ゴルフ場をもつためには、危機や脅威がなくなっては困るわけだ。なぜ米軍は沖縄を手放さないか。ジョンソンはいう。「その答えは明白だ。旧ソ連の軍隊が東ドイツ駐留を楽しんだのと同じ理由から、アメリカ軍も沖縄駐留を楽しんでいるのである。自国の軍事植民地における生活は、ソ連の軍人にとってもアメリカの軍人にとっても、母国ではほとんど望めないほどすばらしいものなのだ」。沖縄は「ペンタゴンの軍事植民地」であり、軍人とその家族にとって、「アメリカでは決して体験できないことを体験できる巨大な隠れ家なのだ」という(『アメリカ帝国への報復』集英社)。この快適な「植民地」を維持するために、脅威や危機はいくらでも作れるわけだ。だか、そんな「自己チュー」に付き合わされる方はたまったものではない。米軍のトランスフォーメーションのなかで、米陸軍第1軍団司令部が座間に進出する計画だが、第1軍団の任務は米国が「不安定な弧」と勝手に決めつけたアジア・中東地域を、軍事的に管理・統制することである。この米軍戦略の展開に応じて、この地域における新たな紛争が「紛争らしく」顕在化してくるだろう。マスコミがまたそれをセンセーショナルに伝え、米軍の「仕事」が確保されていく。日米安保条約6条(極東条項)に基づく基地使用条件は、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」であるが、第1軍団司令部が担任するであろう「不安定な弧」は「極東」よりはるかに広大な地域である。当然、この極東条項との抵触が危惧されるところである。そこで最近、米側は第1軍団司令部の作戦指揮を極東地域に限定するかのような態度をとりはじめている(『東京新聞』4月7日付)。日本の国内世論向けの説明であることは明らかであり、そのまま信じることはできない。この夏にも「新・新日米安保共同宣言」が予定されている(『読売新聞』1月14日付「スクープ」〔先触れ〕記事参照)。1996年の「新日米安保共同宣言」が「アジア・太平洋地域の安定」を日米の「死活的利益」にカウントしたが、2005年の「新・新日米安保共同宣言」は、日米安保体制が「グローバル安保体制」に転換する契機となるだろう。
米軍再編の影響は日本だけにとどまらない。99年のドイツ滞在中、ドイツ駐留の米軍基地を車で見てまわった。米軍基地が多いラインラント・プファルツ州の田舎道を走っているとき、戦車が目の前を横切っていったのには仰天した。3月26日のドイツニュースに流れた情報によると、そのドイツ駐留米軍7万人の60%が削減されるという。その代わり、米軍は、「新しいヨーロッパ」(東欧)に新たに進出し、ルーマニア、ブルガリア、ポーランドに新たな米軍基地がつくられる。タジキスタンとキルギスタンの基地は訓練用となるという。「不安定な弧」を東西両翼から軍事的に統制するため、第1軍団司令部の座間進出を軸に再編が進む在日米軍基地と、「新しいヨーロッパ」の新たな米軍基地は、その重要な拠点となろう。まさに「不安定な弧」に対する「前方展開」である。
他方、在韓米軍3万7000人のうち、すでに第2師団主力から1万2500人の削減が公表されている。2年半前、米第2師団が駐留する町を訪れたことがあるが、「基地の町」には、自治体への補助金から犯罪・売春に至るまで、共通する病理現象が確認できる。基地によって「潤う」ことは、豊かさの証ではない。「基地がなくなると困る」という町は、麻薬患者と似ている。新たな軍事基地が出来る地域では、同じ問題を抱える。軍隊というものが、その組織温存のために不自然で過剰な自己主張をはじめるとき、周囲は不幸になる。最悪の場合は、戦争。そしてクーデタ。さらには演習・訓練による環境破壊から、兵士による犯罪に至るまで、およそ生産的で創造的なエネルギーとは無縁のオーラを発信しつづけるのが軍隊である。映画「戦争のはじめかた」が示唆するように、武力を背後にもつ組織が組織を温存する最も効果的な方法は、適度な緊張状態の創出である。大規模戦争は必要ない。二つの手法を組み合わせればよい。一つは、どこに潜むかもわからないテロリストとのたたかい(「対テロ戦争」)に備えた、全方位の警戒態勢である。テロとのたたかいは「ネバー・エンディング」だから、予算が削減されることはない。「対テロ戦争」は軍隊の存続と軍事費の安定供給源である。もう一つ、「同盟国」を含めて米軍に協力する態勢を維持するためには、特定の国を明示した地域的な重点布陣が必要となる。そのための「口実」が、「テロ支援国家」、「ならず者国家」、「悪の枢軸」ときて、いま、「圧制の前哨(拠点)」(ライス国務長官)となったわけである。そこには、米軍基地ができたイラクと、恭順の意を表したリビア、シリアもスーダンも含まれていない。残るはイランと北朝鮮、キューバ。これに、ベラルーシ(旧ソ連邦の白ロシア共和国)とジンバブエ(アフリカ)、ミャンマーが入った。「圧制の前哨」の点と点をつなぐと、米軍と同盟国軍のグローバル展開の面はすべてカバーされている。「テロ支援国家」や「大量破壊兵器」とは無縁のベラルーシやミャンマーまで含むのは、イラク戦争の最後の段階で押し出されてきた「民主化」という「大義」と照応するだろう。「圧制の前哨」を除去するための「自由と民主主義のための軍事介入」というわけである。だが、「圧制」か否かの判断はすべて米国(ブッシュ政権)が行い、判断基準も著しく恣意的である。ベラルーシよりもサウジアラビアの方が「民主的」なのか。ロシアや中国は「圧制」をやっていないか。どんな独裁政権でも、外からの軍事介入で倒してよいのか。それで本当に民主主義は定着するか。でも、そんな疑問や批判は、ブッシュ政権にとっては「想定内」のことで、どこ吹く風だろう。「圧制」を除去したあとの「民主化」は「アメリカ化」と同義なのだから。言い換えれば、軍隊の海外出動とその拠点(基地)の海外展開は、軍隊と軍需産業にとって有効「需要」創出装置なのであり、逆にいえば、その「需要」がある限り、「テロ」や地域紛争の「供給」がなくなることはない。それは、「世界中の民主化(アメリカ化)」が完成するまで続く。映画「戦争のはじめかた」のラストは、私には、この「連鎖」を示唆しているように思えてならない。
そうしたなかで、日本国憲法9条は、一国民国家の憲法であるにもかかわらず、世界の人々に、「戦争のおわりかた」を構想させるヒントを与えているように思う。1999年5月、オランダのデン・ハーグで開かれたハーグ市民社会会議(全世界から9000人のNGOなどが参加)では、「公正な世界秩序を求める基本原則」10項目が採択された。その第1項は「日本国憲法第9条が定めるように、世界諸国の議会は、政府が戦争をすることを禁止する決議を採択すべきである」であった。「日本国憲法第9条」という文言が、世界のNGOの決議に初めて入ったのは象徴的である。9条1項が1928年の「不戦条約」以来の「戦争違法化」の世界的スタンダードを示すものだとすれば、戦力不保持と交戦権否認を定めた9条2項こそ、21世紀における世界平和の新しいスタンダードになりつつあるのではないか。「日本国憲法第9条の含意」は、「各『国民国家』による世界編成から、段階的な発展過程を経て、『公正で民主的な世界連邦』の実現」へと向かう射程と広がりをもつとされる所以である(浦田賢治「ハーグ市民社会会議の憲法学的課題」『二一世紀の立憲主義』〔勁草書房〕244頁)。いま、「軍隊のおわりかた」についても、真剣に考える「とき」であろう。
なお、昨5月8日は、ドイツでは「戦争のおわりかた」を思い起こす60周年の無条件降伏記念日であった。
 この作品は2001年9月のカナダ・トロント国際映画祭で、会場を騒然とさせた。そして、全米で上映されようとしたまさにそのときに「9.11」が起きて、あえなくお蔵入りとなった。アフガン戦争、イラク戦争と続いて、全米公開が5度も延期になった。館内で購入したパンフレットには、「不謹慎なつくりごと」ではなく「真実がここにある」とある。米軍基地内部の話なのに、英・独合作(2001年)である点も面白い。「愛国心」を強調する米国の場合、自国軍隊の矛盾や腐敗をここまで徹底して暴き、コケにするのは難しいかもしれない。
この作品は2001年9月のカナダ・トロント国際映画祭で、会場を騒然とさせた。そして、全米で上映されようとしたまさにそのときに「9.11」が起きて、あえなくお蔵入りとなった。アフガン戦争、イラク戦争と続いて、全米公開が5度も延期になった。館内で購入したパンフレットには、「不謹慎なつくりごと」ではなく「真実がここにある」とある。米軍基地内部の話なのに、英・独合作(2001年)である点も面白い。「愛国心」を強調する米国の場合、自国軍隊の矛盾や腐敗をここまで徹底して暴き、コケにするのは難しいかもしれない。