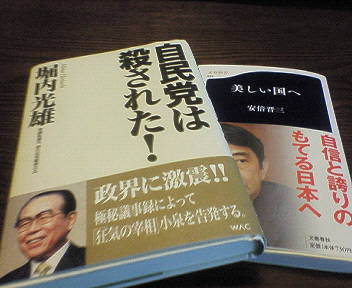「失われた5年」と「失われる○年」――安倍総裁、総理へ 2006年9月25日
9月2日、広島市内で講演した。 広島行きの便は福岡から来た飛行機を使ったので、機内サービスの新聞は、各紙すべて西部本社版(福岡)だった。『読売新聞』を手にとると、原爆ドームを背に、安倍晋三のカラー写真が掲載されている。自宅を出る前に見てきた同紙東京本社版の見出しや写真の色合いとは微妙に異なる。私が広島に入る前日、安倍が、南区の広島プリンスホテルで開かれた自民党員集会で、総裁選に立候補する決意を表明していたのだ。「なぜ、第一声が広島なのか?」と思いつつ、新聞に目を走らせると、地元の『中国新聞』はベタ記事に近い扱いで、写真も使っていない。他紙は、ホテル会場で演説する安倍の写真を一面に使い、大きな扱いにしたのとは対照的だった。安倍の「ヒロシマ」利用を同紙が意識的に拒否したようにも見える。『読売』だけが、「原爆ドームと安倍晋三」の組み合わせ写真を載せたことになる。「核兵器の保有は直ちに違憲ではない」という見解を表明し、原爆ドームと最も距離のある政治家と見られてきた人物が、第一声の地として「ヒロシマ」を選んだのは、単なる偶然か。それは、「広島で『タカ派』払しょく?」という『読売』の見出しで説明できるように思う。アジアのメディアが、『読売』写真と同じアングルを使ったかどうかは確認していないが、第一声のロケーションとしては、国内外に向け「平和」をアピールできるという意図はうかがえるだろう。
広島行きの便は福岡から来た飛行機を使ったので、機内サービスの新聞は、各紙すべて西部本社版(福岡)だった。『読売新聞』を手にとると、原爆ドームを背に、安倍晋三のカラー写真が掲載されている。自宅を出る前に見てきた同紙東京本社版の見出しや写真の色合いとは微妙に異なる。私が広島に入る前日、安倍が、南区の広島プリンスホテルで開かれた自民党員集会で、総裁選に立候補する決意を表明していたのだ。「なぜ、第一声が広島なのか?」と思いつつ、新聞に目を走らせると、地元の『中国新聞』はベタ記事に近い扱いで、写真も使っていない。他紙は、ホテル会場で演説する安倍の写真を一面に使い、大きな扱いにしたのとは対照的だった。安倍の「ヒロシマ」利用を同紙が意識的に拒否したようにも見える。『読売』だけが、「原爆ドームと安倍晋三」の組み合わせ写真を載せたことになる。「核兵器の保有は直ちに違憲ではない」という見解を表明し、原爆ドームと最も距離のある政治家と見られてきた人物が、第一声の地として「ヒロシマ」を選んだのは、単なる偶然か。それは、「広島で『タカ派』払しょく?」という『読売』の見出しで説明できるように思う。アジアのメディアが、『読売』写真と同じアングルを使ったかどうかは確認していないが、第一声のロケーションとしては、国内外に向け「平和」をアピールできるという意図はうかがえるだろう。
さて、先週、9月20日午後、安倍自民党「総裁」が誕生した。任期は3年である。明日26日には内閣「総理」大臣に就任する予定である。「総理・総裁」という、他国では理解できない「・」でつながる不思議な言葉。一政党のトップがあたかも自動的に首相になるかの如き状況が、この国では普通に起きている(細川・羽田・村山内閣のときの河野自民党総裁だけが例外)。メディアの関心は、目先の自民党役員人事、組閣の中身(大臣の顔ぶれ)に集中している。「サプライズはあるか」といった、実はどうでもいいことに、「専門家」が真面目な顔をしてコメントしている。
自民党の総裁選挙管理委員会は8月28日、党員投票の選挙人数を発表した。それによると、04年、05年と連続党費を納めた党員・党友による選挙人数は106万8665人。郵政民営化法案に反対して離党した人々が大量に出たため、前回総裁選の03年の140万2621人よりも20%以上の減という(『毎日新聞』8月29日付)。5分の4以下の選挙人で行われた総裁選挙。選挙人2割減は、「自民党をぶち壊す」と言った小泉の実践の帰結でもある。このことは記憶しておく必要がある。
安倍政権発足の本質的な問題は、安倍が何をやるか、である。安倍晋三という人物の思想と行動が、一議員や一閣僚(官房長官)にとどまっていた段階とは異なり、いよいよ内閣総理大臣という最高ポストを得て、本格的に動きだす。その危なさは、交通法規〔憲法〕を確信犯的に無視するドライバーが、大型トラックの運転席に座り、道路に走り出したのに近い。このトラックは行く先々で、たくさんのトラブルを起こすだろう。ドライバーは、饒舌に語りながら、「お目々キラキラ、真っ直ぐに」トラックを走らせていくのだろう。この国の不幸は続く。
その安倍政権の危なさについて具体的に語る前に、明日、総理を退く小泉純一郎が政権を担当した5年に対する私の感想を書いておこう。「失われた5年」。これをもたらした小泉について、この「直言」で何度も言及してきた。彼が残した「迷言」も多い。「憲法前文と9条のすきま」を語り、憲法前文をつまみ食い的に読み上げ、「イラク派兵」には「瞬間タッチ断言法」で応答した。政権発足当初は首相公選論に関心を示したものの、改憲を必要とする面倒な話はサッと切り上げ、パフォーマンスの活用に転じた。拉致問題の政治的利用、郵政民営化、「今のうち解散」と「郵政解散」という二回の解散。そこにみる強引な政治手法など、小泉政治が残したマイナスは大きい。そして、沖縄国際大ヘリ墜落事件と新潟県中部地震、最近では加藤紘一・元自民党幹事長宅放火事件の際に示されたように、「趣味に生きる」首相らしく、自分の関心が向かないことに対しては徹底して冷たい。さらに、周辺諸国との関係において大切な歴史認識や「記念日」への無頓着。米国もびっくりの対米追随姿勢などである。「自民党をぶち壊す」も歴史的な言葉となった。「9.11総選挙」を経て、「云いたいことは なんでも云える 自由がここに あるんだぜ 話しあおうよ どこまでも」という自民党結党14年の歌「話しあいのマーチ」(水前寺清子)の精神は消え失せた。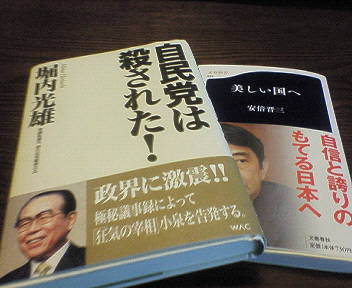 いまや自民党は、粛清(「刺客」)や中央集権制など、スターリン主義党とよく似た体質が見えてきた。自民党総務会長をやった堀内光雄の『自民党は殺された!』 (WAC) がそのあたりをリアルに描写している(「直言」の末尾に書名を挙げた)。
いまや自民党は、粛清(「刺客」)や中央集権制など、スターリン主義党とよく似た体質が見えてきた。自民党総務会長をやった堀内光雄の『自民党は殺された!』 (WAC) がそのあたりをリアルに描写している(「直言」の末尾に書名を挙げた)。
そうした小泉が発した言葉のなかで、あまり知られていない一つに、「何かピンチになると、逆境に入ると、なんかいい風が吹いてくるんですねえ」がある。06年2月24日、都内のホテルで開かれた会合での挨拶でのことである。
1月16日にライブドアに対する強制捜査が始まり、「9.11総選挙」における自民党幹事長・武部勤や総務相の竹中平蔵と「ホリエモン」との密接な関係が問題となり、2月16日、民主党の若手議員による「メール問題」追及が始まった。「4点セット」(7か月前のことだが、すべてご記憶の方が何人いるだろうか?また、参照『憲法「私」論』「はじめに」)、小泉は大変な危機のはずだった。だが、小泉は難なくそれを乗り切った。
それからもう一つ。「小泉内閣メールマガジン」第229号(06年4月6日午前7時受信)首相メッセージ「らいおんはーと」。タイトルは「初心忘るべからず」。金メダリストの荒川静香とオペラ「トゥーランドット」を鑑賞したことを得々と書き、こう続ける。「総理に就任して5年近く。一人の平凡な人間が、ここまでやってこられたのは、多くの国民のみなさんのご支援、ご協力があったこと、そして運が良かったことだと思います。いつも何かに守られている、国民のみなさんが支持してくれている、運がいいな、と思いながら、精一杯頑張らなければならないと思っています」。この二つの言葉から、小泉は、自らの「運のよさ」を自覚している。まさに「怖いものなし」の暴走トラックだった。なお、「運がいいな」という言葉は、「小泉内閣メールマガジン」最終号(第250号)(9月21日午前7時送信)でも繰り返されている。
この小泉政権は、当初は、保守勢力の内部でも「想定外」だった。それを可能にしたのは、支持率一桁台という驚異的不人気を誇ったあの森喜朗内閣のおかげである(なお、森は「前首相」から「元首相」になったので、今回の「直言」以降、「あの男」ではなく、「森元首相」と呼ぶことにする)。
この森内閣誕生について、私は一貫して疑問視してきた。この疑問を解いてくれる「証言」が近年あらわれた。「密室」の当事者の一人、村上正邦・元自民党参議院会長の「密室の謀議」というインタビュー記事である(『週刊新潮』2006年5月25日号)。村上は、「有珠山」は作り話だった、とはっきり述べている。「やはり」と思った。「有珠山の噴火の件もあるので、よろしく」と小渕首相から言われたので、と当時の青木官房長官ははっきり述べていた。これが、首相から官房長官への臨時代理の委任と受けとられた。小渕はそのとき意識不明で、そんなことを語れる状態になかったことは、後にわかった。まさに「作り話」と嘘を重ねて、「首相の座」が森喜朗の手にわたったのである。そして、その森の失点続きが、国民の支持を大きく失い、小泉の登場を準備したのである。森があそこまで失政を重ねなければ、小泉純一郎という「変人」が自民党総裁になることはなかっただろう。私は小泉政権発足当初に、驚異的支持率について、「バブル総理」と書いた(01年5月1日)。こうして見ると、結果的に、安倍内閣の誕生は、「森首相」の登場が原因だったとも言える。小渕がもう少し長生きすれば、森内閣もなかっただろうし、森内閣がなければ、あの「永田町の奇人」にして、「国家趣味者」の小泉純一郎が「総理・総裁」になることもなかっただろう。
小泉政権5年間は、冷酷無情な「決断政治」と、「説得せず、調整せず、妥協せず」の「三無主義のニヒリズム」(御厨貴東大教授)のゆえに「唯一無二の無調整政権」(『毎日新聞』9月8日「記者の目」)と評された。その上で、国のかたちを定め、権力を制限する憲法に対して、総じて「憲法ニヒリズム」を蔓延させた。慶応大で同級生の栗本慎一郎の言葉によれば、小泉は、無情や非情のレヴェルではなく、まさに感情がないという意味での「欠情」の域に達しているという。側近中の側近、首相秘書官の飯島勲も、「いざという決断の時、侠客的な…すごみを見せます。これが強みですね」と語っている(『毎日新聞』9月15日付)。前掲「小泉内閣メールマガジン」最終号で、小泉自身も「非情」という言葉を使っている。中途半端な情がない分、国民に「無数の痛み」をもたらす「改革」が実行可能だったとも言えよう。
さて、挙げていけばきりがない小泉の具体的な政策のなかで、一つだけ、「イラク復興支援」の「その後」を取り上げておこう。
日本の対外政策上の「原則」ともなっていた「海外派兵」禁止。これは、「海外派遣」はOKという政府解釈をベースに、90年代はじめ頃からさみだれ式に海外への自衛隊の派遣が続いた。「海外派兵」とは「武力行使の目的をもって、武装した部隊を、他国の領土、領海、領空に派遣すること」であって、これは自衛のための必要最小限度を超えるので許されない、と政府は解釈してきた。かつてなら国会で「海外派兵」にあたると追及され、国会が空転するくらいの「派遣」が行われるようになった。03年3月20日に米国が始めた、国際法違反の侵略戦争。これを小泉は丸ごと支持し、「イラク復興支援」という名目で、重装備の陸自部隊をイラクに派遣した。その時の論理を思い出してほしい。「ここでイラク派遣に協力しておかないと、北朝鮮との問題が起きたときに米国が助けてくれない。日米同盟こそが大切だ」と。その後、「撤退」を「撤収」と言い換えて、陸自部隊は帰国したが、6月20日、イラク特措法に基づく実施計画の変更の閣議決定により、航空自衛隊の輸送航空隊を、「戦闘地域」のバクダッドなどの輸送活動に従事できるようにした。このことはすでに批判した。
最近、米軍関係のメールマガジン(9月9日付)を見ていたら、9月6日、「その52年の歴史のなかで初めて」、航空自衛隊は、国連の新しいミッションの最初のフライト(C-130機) がバクダット国際空港に無事に着陸したと書いてあった。
注目すべきは、国連のミッションだけでなく、多国籍軍部隊(当然に米軍を含む)の輸送にもあたることだろう。 派遣部隊の一空佐は、イラクの安全と「テロとのグローバルな戦争」の勝利に日本が貢献することを得々と語っている。調子に乗った一空佐は、「イラク戦争支援における日本の輸送作戦」と呼び、米軍を含む多国籍軍部隊の輸送を明言している。「これは非常に意義深いイベントである」とし、「我々のパートナーシップが、日米同盟の強化に貢献してきたと信ずる」と述べている。イラク特措法は、「非戦闘地域」において「復興支援」にあたることを授権したものである。この一空佐が述べたことは、「非戦闘地域」ではないバグダット空港などから、米軍の軍事要員などを輸送する戦闘作戦行動と完全に一体化した、兵站業務を担任したことを素直に告白したものである。これはイラク特措法に抵触する。戦闘地域への活動を拡大した実施要領の変更は、法律本体の目的規定に反するものだろう。内閣法制局のチェック機能も落ちたものである。
派遣部隊の一空佐は、イラクの安全と「テロとのグローバルな戦争」の勝利に日本が貢献することを得々と語っている。調子に乗った一空佐は、「イラク戦争支援における日本の輸送作戦」と呼び、米軍を含む多国籍軍部隊の輸送を明言している。「これは非常に意義深いイベントである」とし、「我々のパートナーシップが、日米同盟の強化に貢献してきたと信ずる」と述べている。イラク特措法は、「非戦闘地域」において「復興支援」にあたることを授権したものである。この一空佐が述べたことは、「非戦闘地域」ではないバグダット空港などから、米軍の軍事要員などを輸送する戦闘作戦行動と完全に一体化した、兵站業務を担任したことを素直に告白したものである。これはイラク特措法に抵触する。戦闘地域への活動を拡大した実施要領の変更は、法律本体の目的規定に反するものだろう。内閣法制局のチェック機能も落ちたものである。
 小泉がそういうお膳立てをしてから、米国訪問を行い、ブッシュと大統領専用機「エアフォースワン」で、歌手エルビス・プレスリーゆかりの場所を訪れた。7月1日付各紙夕刊が載せた写真の見出しのなかに、「歌って踊ってエルビス気分」というのがあった。「趣味で動く首相」の面目躍如だろう。
小泉がそういうお膳立てをしてから、米国訪問を行い、ブッシュと大統領専用機「エアフォースワン」で、歌手エルビス・プレスリーゆかりの場所を訪れた。7月1日付各紙夕刊が載せた写真の見出しのなかに、「歌って踊ってエルビス気分」というのがあった。「趣味で動く首相」の面目躍如だろう。
小泉政権の「失われた5年」は、この国の立法作法も大きく変えた。この点については、新会社法に関連してすでに書いたので省略する。
さて、安倍は、20日の自民党総裁就任した。「美しい国へ」の内容的空虚さを、ナショナリズムの濃厚な香りで包み、饒舌さがカバーする。総裁選のなかで強調していた三つの政策が、特に危ない。
一つは「5年以内の憲法改正」である。安倍の改憲論は、どこまでもエモーショナルである。2年半前、私は、朝日新聞社の雑誌『論座』で、安倍のムード的改憲論を批判したことがある。こういう改憲を感覚で語る「戦後生まれ」がイニシィアティヴをとるようになった。これは実に危ない。
二つ目は、「日米同盟」妄信と集団的自衛権の行使である。憲法改正をせずとも、これを政府解釈の変更でやるつもりのようである。内閣法制局がこんな解釈を許すなら、存在理由を問われることになろう。
そして三つ目は、重点政策とされる「教育改革」。「愛国心」を正面から打ち出す教育基本法改正は言うまでもないが、「大学9月入学」と「ボランティア」のセットは曲者である。軽薄な私大経営者はすぐに飛びつきそうだ。高校卒業から大学入学までの5カ月間、若者に社会奉仕活動をやらせる(「ボランティア義務」?)を含めて、この人は戦後生まれだが、国家による上からの義務づけが好きらしい。9月入学など、「国際スタンダード」などというが、セメスター制からロー・スクール、教育バウチャー制に至るまで、横文字の仕組みの安易な導入は、さまざまな矛盾を生んでいる。「9月入学」が国際基準だというけれど、「桜満開のなかで入学式」は日本の文化ではないのか。「美しい国」を言うわりには、日本の伝統や文化を本当に大事にしているのか怪しい。
さて、安倍は、「政治的ロマン主義」の香りを漂わせている。饒舌で軽薄な言葉の上に、冷徹で厳格な施策が次々と実施されていくだろう。ただ、ドイツの国法学者カール・シュミットは、ロマン主義的思考の基本性格を偶因論=機会原因論(Okkasionalismus)と捉え、政治的ロマン主義の浮動性を指摘する(カール・シュミット=大久保和郎訳『政治的ロマン主義』〔みすず書房〕206頁)。これは、便宜主義(Opportunismus)に近い。安倍の言説に「政治的ロマン主義」に通ずるものがあるとすれば、それはオポチュニストとしてのそれと重なる面があるかもしれない。
小泉がノリのいい「国家趣味者」だとすれば、安倍はこってり系の「国家主義者」である。危ない以上に、危なすぎる。アジア諸国からはどう見られているか。この間、周辺諸国との人脈も失ってきた。人間の大腸と同様に、国と国とのパイフも短く、細く、つまっていれば当然、不具合をおこす。
ドイツの高級週刊誌『シュピーゲル』は、安倍のことを「イランのマフムード・アフマディーネジャード大統領と似ている」と書いた。一部でも報道されたが、これはこういう脈絡である。小泉の8.15靖国参拝の問題を論ずるなかで、安倍は戦前の日本の戦争犯罪を認めず、東京裁判の判決に関しても歴史家によって明確にされるべしと語ったことをとらえ、「この点で、安倍は、ホロコーストに関して、あたかも補足や説明が必要であるかのように『専門家』に研究させたがっているイラン大統領と似ている」(W. Wagner, Pilgern zum Schrein, in: DER SPIEGEL vom 4.9.06, S. 108 f.)。「絶対悪」であるユダヤ人虐殺について、ドイツでは「歴史家」の判断に待つといった態度をとることは許されない。イラン大統領の「専門家」の判断に委ねるという態度に反発を感じるドイツ人からすれば、安倍の態度も同様に映るわけである。なお、「〔総裁〕候補者の世界像」という見出しで、安倍の際立った保守性を、女性天皇に反対する主張に見いだす記事や、「ハードなタカが、ワイルドな改革者のあとに継ぐ」(Harter Falke folgt auf wilden Reformer)という見出しで、改憲に向かう日本に注目する記事も見られた(Die Welt vom 17.9) 。
安倍の安全保障観は、曾祖父譲りで、核兵器の保有それ自体は違憲ではないという解釈をとる。非核三原則などの政策の結果として、核兵器保有ができないにすぎない。「憲法解釈上は、自衛のための必要最小限度を超えなければ核兵器も保有できるが、非核三原則やNPTにより、核保有という選択肢は全くない」(02年6月10日、武力攻撃事態委員会)と。でも、政策を変更すれば、憲法上は核兵器が持てるという解釈になる。これも曲者である。
さらに、安倍は、05年10月25、26日に、 AEI(ネオコン系シンクタンク)所長のクリストファー・デムスや民主党の前原誠司(当時代表)、外務省審議官、防衛研究所副所長(陸将補)らと、国会議事堂裏のホテルで会ったという。何が話し合われたかは報道されていない。だが、そこで、日本と中国を何らかの形で戦争になるようなスケジュールが話し合われたという情報が、ジャーナリストや、評論家の副島隆彦によって流されている。 「(アメリカの仕掛けによって)2008年の北京オリンピックの前にも、東シナ海での散発的な軍事接触のような紛争に日本も巻き込まれるだろう」船井幸雄・副島『昭和史からの警告―戦争への道を阻め』(ビジネス社刊)と。この点は、政治評論家の森田実のサイトで紹介されている(「言わねばならぬ」〔7月10日〕参照)。にわかに信じがたい話だとは思うが、安倍は首相になるいま、1年前のこの会合で何を話し合ったのかを明らかにする義務があるだろう。
総裁の任期は72年までは2年、その後3年になり、78年からまた2年になり、03年から再び3年になった。安倍「総裁」の任期は3年で、三選は禁止されている(「総理」の任期はない。なお、参照「人気があっても任期で辞める意味」)。3年を待たずに、安倍「総理」を終え、「5+○年」を回復できるかがカギになるだろう。
〔文中敬称略〕
トップページへ
 広島行きの便は福岡から来た飛行機を使ったので、機内サービスの新聞は、各紙すべて西部本社版(福岡)だった。『読売新聞』を手にとると、原爆ドームを背に、安倍晋三のカラー写真が掲載されている。自宅を出る前に見てきた同紙東京本社版の見出しや写真の色合いとは微妙に異なる。私が広島に入る前日、安倍が、南区の広島プリンスホテルで開かれた自民党員集会で、総裁選に立候補する決意を表明していたのだ。「なぜ、第一声が広島なのか?」と思いつつ、新聞に目を走らせると、地元の『中国新聞』はベタ記事に近い扱いで、写真も使っていない。他紙は、ホテル会場で演説する安倍の写真を一面に使い、大きな扱いにしたのとは対照的だった。安倍の「ヒロシマ」利用を同紙が意識的に拒否したようにも見える。『読売』だけが、「原爆ドームと安倍晋三」の組み合わせ写真を載せたことになる。「核兵器の保有は直ちに違憲ではない」という見解を表明し、原爆ドームと最も距離のある政治家と見られてきた人物が、第一声の地として「ヒロシマ」を選んだのは、単なる偶然か。それは、「広島で『タカ派』払しょく?」という『読売』の見出しで説明できるように思う。アジアのメディアが、『読売』写真と同じアングルを使ったかどうかは確認していないが、第一声のロケーションとしては、国内外に向け「平和」をアピールできるという意図はうかがえるだろう。
広島行きの便は福岡から来た飛行機を使ったので、機内サービスの新聞は、各紙すべて西部本社版(福岡)だった。『読売新聞』を手にとると、原爆ドームを背に、安倍晋三のカラー写真が掲載されている。自宅を出る前に見てきた同紙東京本社版の見出しや写真の色合いとは微妙に異なる。私が広島に入る前日、安倍が、南区の広島プリンスホテルで開かれた自民党員集会で、総裁選に立候補する決意を表明していたのだ。「なぜ、第一声が広島なのか?」と思いつつ、新聞に目を走らせると、地元の『中国新聞』はベタ記事に近い扱いで、写真も使っていない。他紙は、ホテル会場で演説する安倍の写真を一面に使い、大きな扱いにしたのとは対照的だった。安倍の「ヒロシマ」利用を同紙が意識的に拒否したようにも見える。『読売』だけが、「原爆ドームと安倍晋三」の組み合わせ写真を載せたことになる。「核兵器の保有は直ちに違憲ではない」という見解を表明し、原爆ドームと最も距離のある政治家と見られてきた人物が、第一声の地として「ヒロシマ」を選んだのは、単なる偶然か。それは、「広島で『タカ派』払しょく?」という『読売』の見出しで説明できるように思う。アジアのメディアが、『読売』写真と同じアングルを使ったかどうかは確認していないが、第一声のロケーションとしては、国内外に向け「平和」をアピールできるという意図はうかがえるだろう。