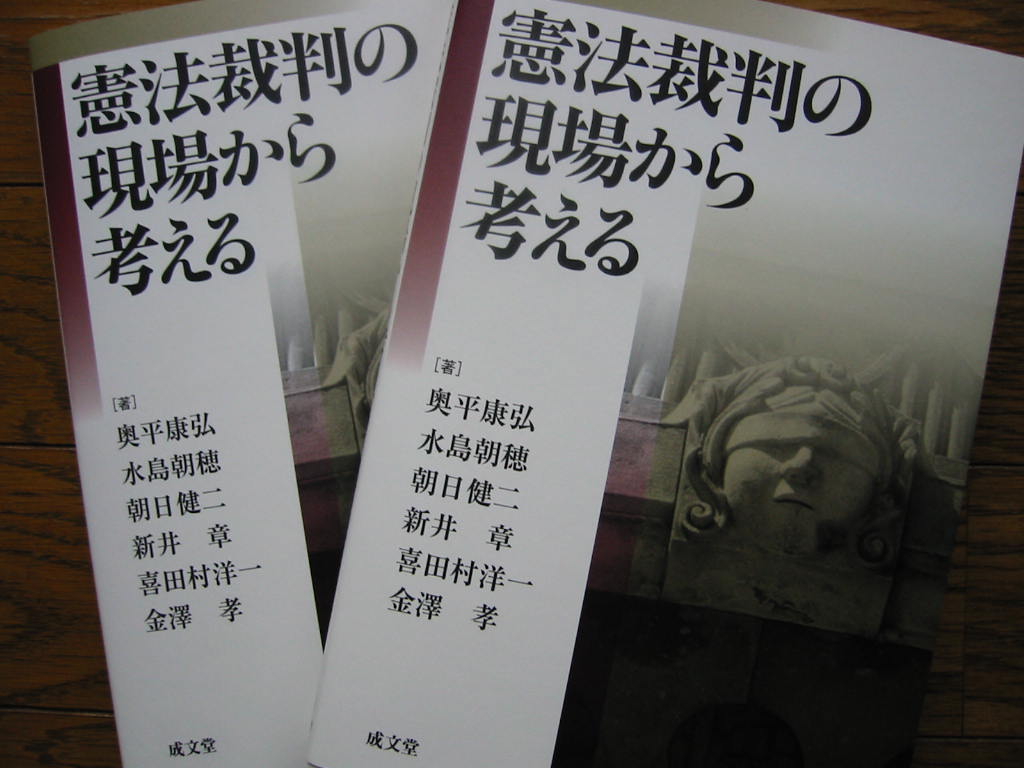
昨年末に『憲法裁判の現場から考える』という編著を出版した。2010年に行った早稲田大学法学部主催「横川敏雄記念講座」の講演をすべて収録したものである。憲法学界におけるこの問題の第一人者である奥平康弘氏、生存権の「朝日訴訟」の原告である朝日健二氏、教科書検定違憲訴訟弁護団の中心におられた新井章氏、海外在住というだけで一票を行使できなかったことに対して、最高裁が公職選挙法の当該規定を違憲と判断し、5000円の損害賠償を命じた「在外邦人選挙権制限違憲訴訟」弁護団の喜田村洋一氏、そして、長沼事件で自衛隊違憲判決を出した札幌地裁福島重雄裁判長にインタビューして本の形にまとめた水島。この5人の講演を再現し、憲法裁判に関する解説(編者の金澤孝執筆)を加えたものである。お読み頂ければ幸いである。
さて、「最高裁は変わった」という声を聞くようになった。従来から最高裁は憲法判断に消極的だという評価が定着していた。実際、法令違憲の判決は7種類8件【注】にすぎない。処分違憲(公権力機関の権力行使に対する違憲判断)の判決もさほど多くはない。そこから日本の最高裁は「司法消極主義」をとっているとされる。ただ、その最高裁にも、このところ微妙な「変化の兆し」が生まれている。
例えば、昨年3月23日の衆議院議員定数不均衡訴訟判決。結論は選挙区割りが投票価値の平等に反する「違憲状態」にあったというものだが、そこに個別意見が5つも付いた(補足意見2、意見1、反対意見2)。違憲とする反対意見は2人なので、表面的には13対2の判決に見えるが、「1人別枠方式」(300小選挙区のうち、まず47都道府県に1人ずつ割り当て、残りの253議席を人口比例で配分する方式。94年に現行選挙制度を導入するとき、地方の現職議員に配慮した「激変緩和策」である)については、憲法上問題なしとした裁判官は1人だけだった。つまり14対1で「1人別枠方式」は較差を生む「主要な要因」と断定されたのである。これを受けて国会は、「1人別枠方式」廃止のための公選法改正へと動き出した。
このように、近年の最高裁は、違憲判断を正面から打ち出すというわけではないものの、個々の施策に対して立法府の裁量に丸投げせずに、細かな注文をつけるようになった。東日本大震災直後で世間的には注目されなかったこの判決の意味を早い時期に浮き彫りにしたものとして、宍戸常寿「最高裁判決で拓かれた『一票の較差』」(『世界』2011年6月号)がある。なお、最高裁の判断の背後には、この定数不均衡訴訟における全国の高等裁判所(選挙に関する訴訟では高裁が第一審)の判断が、違憲4件、違憲状態3件、合憲2件と三分されたことも大きい。「最高裁が変わった」ということの後には、下級審における変化があることも見逃せない。拙編著『憲法裁判の現場から考える』では、奥平氏が「変化の兆し」(第1章第7節)として指摘し、金澤氏がより詳しく検討しているので参照されたい(第6章)。
「変化の兆し」と言えば、昨年の「君が代訴訟」の判決群もそうである。合憲か違憲かで分ければ、表面上は合憲判決であることに変わりはない。昨年5月20日に出された第2小法廷判決に始まり、第1小法廷(6月6日)、第3小法廷(6月14日)と、短期間に最高裁が相次いで同種の事件で判決を出した。結論は、いずれも、君が代の起立斉唱を命じる学校長の職務命令は、憲法19条の思想・良心の自由に違反しないというもので、最高裁長官を含む15人の裁判官が、3つある小法廷(5人)すべてにおいて個々に合憲判決を出すことで、「持ち回り合憲判決」とも評された。この「直言」では、最初の第2小法廷判決を詳細に検討したが、そこでの特徴は、個々の裁判官の補足意見がいくつも付いていたことである。それを読めば、思想・良心の自由の「間接的制約」の可能性を指摘しつつ、教育現場での起立斉唱を求める職務命令の危うさを示唆している。「紙一重の合憲性」とされる所以である。
そして先週1月16日、その最高裁が当該職務命令を合憲としながらも、個々の処分の中身に踏み込んだ判断を示し、2人の原告に対する処分を取り消したのである。これは「変化の兆し」のさらなる現れとして注目される。少し詳しく見ておこう。
この最高裁第1小法廷2012年1月16日判決は、学校の式典で日の丸に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかった公立学校教員に対して東京都が行った懲戒処分について、「過去数回の不起立のみで停職・減給とするのは、処分による不利益の大きさを考慮すると重すぎて違法」という判断を示し、停職1カ月の元教員と減給10分の1(1カ月)の元教員の処分を取り消した。その一方で、戒告処分の教員と、卒業式の国旗掲揚を妨害し、校長の対応を批判する文書を生徒に配った教員に対する停職3カ月の処分は「裁量権の濫用とは言えない」として取り消さなかった。損害賠償請求については、停職処分を取り消した1人ついてのみ、審理を東京高裁に差し戻し、残りはすべて棄却した。
公務員の懲戒処分で最も重いのは免職である。次が停職、減給、戒告の順になる。どの処分を選択するかは、懲戒権者の裁量に委ねられる。裁判所がそれを問題にできるのは、裁量権の逸脱(踰越)や濫用があった場合である。法が許容する裁量の範囲を逸脱した場合、また許容の範囲内であったとしても、法の趣旨に反して行使されるなどした場合(濫用)には、処分が取り消されることがある。
本件では、東京都教育委員会が懲戒処分の量定(軽重をはかって決定すること)に際して、過去に懲戒処分を受けたにもかかわらず、同様の行為を行った場合に量定を加重するという「処分量定」の方針を明確にした、2003年のいわゆる「10.23通達」が問題とされた。これによると、起立しない教員は、1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目は停職となる。
最高裁第1小法廷の多数意見(5人中4人)は、職務命令の合憲性については昨年5~6月の判例を引用しつつ合憲とした。そして、学校の規律や秩序保持等の目的から、重きに失しない範囲で懲戒処分をなすことは、基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内に属するとした。しかし、懲戒処分の選択にあたっては、「戒告を超えてより重い減給以上の処分」をする場合には、事案の性質などを踏まえた慎重な考慮を求めている。特に停職処分は職務の停止や給与全額が支給されないという不利益があり、将来の昇給等にも影響が及ぶ上、「懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していく」ので、停職処分が許されるのは、過去の処分歴などからみて、学校の規律や秩序の保持等の必要性と、処分による不利益の内容との権衡〔バランス〕から処分の相当性を基礎づける具体的事情が認められる必要があるとした。
この観点から上告人らの具体的事情の考慮に入り、「過去2年度の3回の卒業式等における不起立行為による懲戒処分を受けていることのみを理由に同上告人に対する懲戒処分として停職処分を選択した都教委の判断は、停職期間の長短にかかわらず、処分の選択が重きに失するものとして社会通念上著しく妥当を欠き、上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法の評価を免れない」として、停職処分の2人のうちの1人の処分を取り消した。減給処分の1人についても、ほぼ同様の理由から処分を取り消した。
他方、停職処分になったもう1人ついては、不起立以外の処分3回と不起立行為による処分2回があり、そのうちには、卒業式における国旗掲揚の妨害・引き降ろし行為などが含まれていることを指摘して、「停職処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情があった」と認定。処分の選択について裁量権の逸脱・濫用はないと判断した。また、過去に同種の行為(不起立)による処分歴のない教員らに戒告処分を行った都教委の判断も、「社会通念上著しく妥当を欠くものとはいえず、上記戒告処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえない」とした。
停職処分になった2人の教員について、よく似た表現を用いながらも、裁判所の判断は正反対になっている。いかなる処分を選択するかは懲戒権者の裁量に属するという前提に立ちながら、戒告と「減給以上」との間に線引きをすることは、「減給以上」の裁量を収縮させる効果をもつ。なぜ、「減給以上」の処分に慎重さが求められるのか。この点、旧労働省女性局長などを歴任した行政官出身の桜井龍子裁判官は、公務員懲戒制度における処分の加重について補足意見を書いている。それによると、加重のあり方には法令上の根拠がないため、加重処分が裁量の範囲内といえるためには、より慎重な判断が要求される。都教委の「10.23通達」が1回目戒告、2回目減給1カ月、3回目減給6か月、4回目以降は停職という方針をとっていることについて、減給や停職が与える不利益の内容を詳しく述べながら、「一律の加重処分の定め方、実際の機械的な適用」そのものが問題であると指摘している。そして、懲戒処分が繰り返される教育現場のあり方は容認できないとして、「自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれる」と付言している。
ただ1人反対意見を書いた宮川光治裁判官は、昨年6月の第1小法廷判決でも、職務命令は憲法19条違反であるという反対意見を書いており、今回もその姿勢は崩していない。上告人らが教育公務員である点に着目して、精神の自由はとりわけ尊重されなければならないこと、教育の自由の観点から、公務員であっても、一般行政に携わる者よりも、自由が保障されなければならないことを指摘している。その上で、懲戒処分の裁量審査では、(1)原告らの行為の原因や動機、行為の態様、法益侵害、(2)本件戒告処分は実質的に見ると重い不利益処分であること、(3)他の服務事故(非違行為)に対する処分、他地域の処分例とのバランスを欠いていることの3点について、多数意見との違いを明確にしている。
(1)については、教育者の信念に起因する真摯なものであり、不起立行為は式典妨害を含まない「消極的不作為」にとどまり、式典遂行に物理的支障をきたさないから法益侵害もない、とする。(2)では、戒告が懲戒処分のなかでは最も軽いものの、ボーナス10%減額、昇給3カ月遅れ、退職金・年金支給額の減少に連動する可能性があり、再雇用にもマイナスの影響があり、停職に至る累積処分のスタートに位置するから、戒告といえども「相当に重い不利益処分である」とする。(3)では、体罰やセクハラなどの服務事故(非違行為)を起こした者のうち懲戒処分を受けたのは4分の1にも満たないことから、戒告といえども一般的には非違行為のなかのかなり情状の悪い場合に行われている。また、神奈川、千葉の各県では不起立行為等への懲戒処分が行われていない。以上3点から、宮川裁判官は、戒告処分は「重きに過ぎ、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するもの」と判断している。戒告処分の影響は過少評価できないとして、桜井裁判官よりも、戒告の影響に対する評価は厳しい。
このように、戒告と「減給以上」に線引きをした多数意見も、戒告を含む処分全体を問題にした反対意見も、ともに懲戒処分の量定の選択について、懲戒権者の裁量を収縮させるという点では共通している。この背景として、宮川反対意見も桜井補足意見も、そして、6月の判決で述べた意見を繰り返した金築誠志裁判長の補足意見も、「教育現場のあり方」「教育環境の悪化」「児童・生徒への影響」に言及している点が重要だろう。つまり、一般公務員の処分と異なり、それが教育現場における児童・生徒にも影響することを重視した判断と見られるからである。教育現場でなかったら、ここまで懲戒処分に細かく注文を付けただろうか。
実際、減給処分を取り消された元教員は、養護学校(現特別支援学校)で障害児教育に携わってきた。以前の卒業式は平らな床面で行われ、車いすの児童も介助者なしで卒業証書を取りに行けたが、2003年の「10.23通達」で日の丸が壇上に掲揚され、介助者つきで壇上に上がらざるを得なくなって、「せっかくの晴れ舞台なのに自力で証書を取りにいけない。子どもの気持ちを考えると、黙っていられず、抗議のつもりで初めて起立をやめた」と語っている(『東京新聞』1月17日付)。子どもたちへの熱い想いからやむにやまれぬ不起立という点を最高裁は見逃さなかった。
一方、処分が取り消されなかったもう1人は、もっぱら自己の歴史観・世界観を前面に押し出し、それを子どもたちも理解してくれていると信じて、日の丸を引きずり降ろす行為などを繰り返し、処分を受け続けている。最高裁からすれば、この1人のケースは停職までいってもやむを得ないという判断だろう。
5年前の最高裁「ピアノ伴奏拒否訴訟判決」(2007年2月27日第3小法廷)では、藤田宙靖裁判官(当時)の反対意見が注目された。それは日の丸・君が代についての歴史観・世界観それ自体よりも、むしろ、「公的儀式の場で、公的機関が、参加者にその意に反してでも一律に行動すべく強制することに対する否定的評価(従って、このような行動に自分は参加してはならないという信念ないし信条)」が問題であって、この信念・信条は憲法の保護を受けるという観点から、歴史観・世界観とは別に、斉唱への協力の強制が、この信念・信条に対する「直接的制約」になると述べていた。藤田意見は、学校行政の目的が「子供の教育を受ける利益の達成」にあるとすると、それを達成する手段がピアノ伴奏の強制なのかについて重大な疑いを投げかけ、「教育公務員の職務の公共性」から簡単に思想・良心の自由の制約を導く多数意見を批判した。この藤田意見が打ち出した視点とそれによる裁量統制は、最高裁のなかに少しずつ定着して、学校現場への配慮から、今回のような処分の中身に踏み込んで統制を加えることになったのではないか。
ところで、「大阪維新の会」は、君が代を起立斉唱しない教員に対して、同一の職務命令違反を3回繰り返した場合、分限免職の対象とする「教育基本条例案」を府議会に提出している。今回の判決について、「維新の会」の橋下徹大阪市長と松井一郎大阪府知事は、言い渡しの翌日、条例案の当該規定を見直し、処分前に指導研修の機会を設ける考えを示した(『朝日新聞』1月17日付夕刊)。免職は停職よりもずっと重いので、「処分の選択が重きに失するものとして社会通念上著しく妥当を欠き」違法とされる可能性が高いため、こうした対応になったものと思われる。
最高裁判決を報ずる各紙一面の見出しは、「重い教員処分慎重に」(『朝日新聞』1月17日付)、「不起立で停職・減給違法――『都の処分重すぎる』」(『読売新聞』同)、「君が代訴訟『減給以上慎重に』」(『毎日新聞』同)というものだったが、政治面、社会面では一様に、大阪府の条例案への影響に言及していた。逆に言えば、「処分3回、即免職」という極端な条例案がなければ、最高裁がここまで処分の選択にまで細かく立ち入っただろうか。東京都の「10.23通達」の「戒告→減給×2→停職」という加重を懲戒権者の裁量権の範囲だと認めれば、大阪の条例案への法的歯止めにならないと考え、「減給以上」というよりゆるやかなところに「防波堤」を設けて、大阪の動きを牽制したと言えなくもない。いずれにせよ、この判決もまた、「最高裁が変わってきた」という流れのなかに位置づけられることは間違いないだろう。
(注)最高裁の法令違憲判決
(1)尊属殺重罰規定違憲判決(1973年4月4日)
(2)薬事法距離制限事件判決(1975年4月30日)
(3)1976年衆議院議員定数不均衡事件判決(1976年4月14日)
(4)1985年衆議院議員定数不均衡事件判決(1985年7月17日)
(5)森林法分割制限規定事件判決(1987年4月22日)
(6)郵便法免責規定事件判決(2002年9月11日)
(7)在外邦人選挙権制限違憲訴訟(2005年9月14日)
(8)国籍法違憲判決(2008年6月4日)