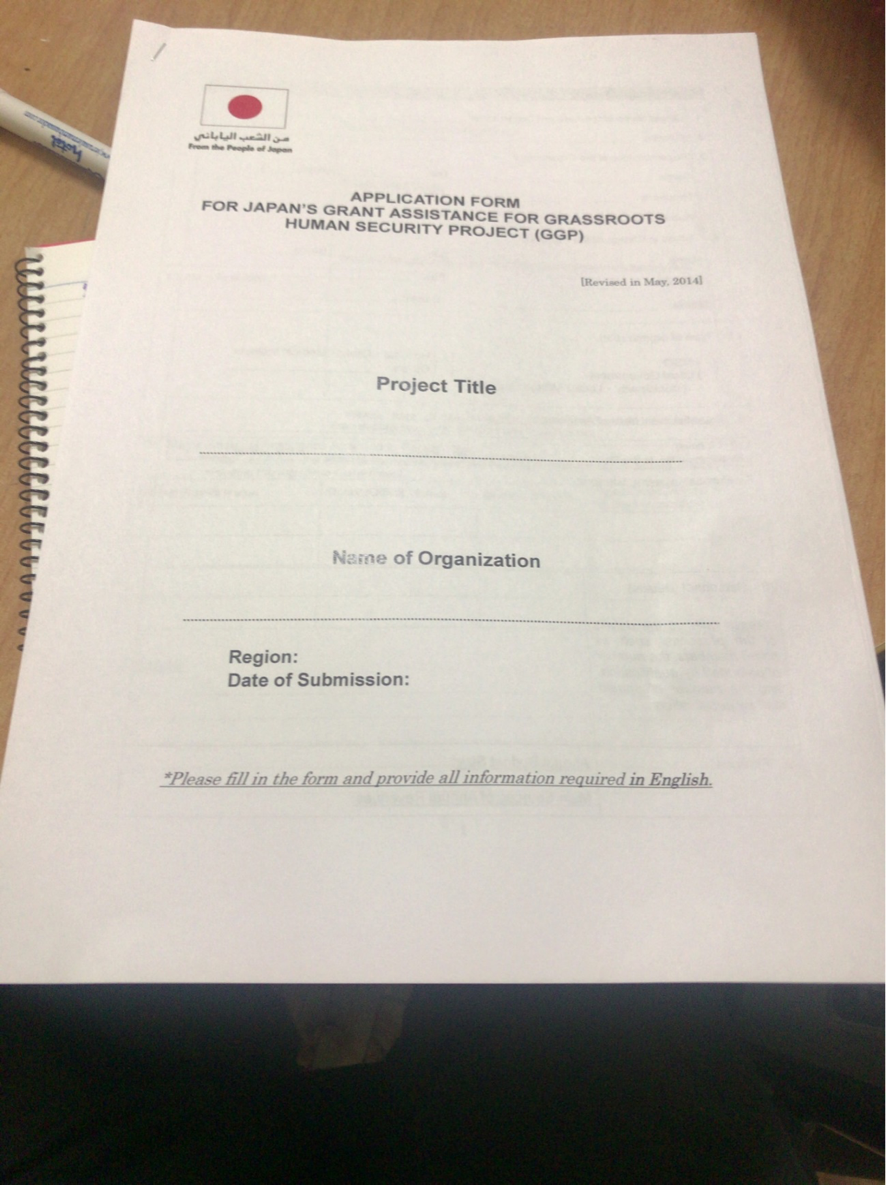トランプの滞在中、ここまでやるかという徹底した「おもてなし」が行われた。想起しよう。2年半ほど前、安倍首相は、25回以上もプーチンと首脳会談を行ったことをことさらに強調し、「(北方領土問題は)私とプーチン大統領とで解決する」と豪語した。だが、プーチンに見事に手玉にとられたことがが、その後明らかになってしまった。北方領土については「0島マイナスα」の悪夢すら想定されている。2016年12月の直言「安倍政権の「媚態外交」、その壮大なる負債」をリンクまでしっかりお読みいただきたい。安倍首相のいう「首脳間の個人的信頼関係」がいかにあてにならないものであるかがわかるだろう。今回のトランプ来日でも、過剰な「おもてなし」戦術が逆手にとられて、8月に巨大爆弾が破裂する可能性が高い。安倍首相はその時、何と言い逃れするのだろうか。次回、「安倍政権の「媚態外交」、その壮大なる負債(その2)——プーチンからトランプへ」として論ずるので参照されたい。
さて、ゼミ22期生のマハール有仁州君の中東取材記、その第2回である(第1回は直言「激動のイスラエルとパレスチナを行く――ゼミ生の取材記⑴」参照)。今回は、いよいよパレスチナ自治区に入る。写真を含め、たくさんのデータがあるが、「直言」の1回分にコンパクトにまとめてもらった。追記として、彼の感想もつけた。
国民国家の果てに—パレスチナ
マハール有仁州(法学部4年、水島ゼミ22期)
前回はイスラエル、特にエルサレム滞在中に目の当たりしたことや自分の思いを綴った。イスラエルとパレスチナの問題について第三者であり、平和な日本で育った自分には何が考えられるだろうか。差別と分断の最前線、パレスチナ自治区に入りさらに考えてみた。
パレスチナ人が背負う不条理な宿命
自治区に入ると同時に、ものものしい分離壁が地平線まで連なり緊張が高まる。自治政府の本部所在地、ラーマッラーは、テルアビブやエルサレムとは打って変わって、アラブ風の街並みが広がっていた。パレスチナに来たので難民キャンプを訪れることにした。通訳を確保するために、街のケバブ屋にいたおじさん達に声をかけた。難民キャンプで暮らす英語を話せる一人のおじさんが案内を引き受けてくれた。ナセルさんという。この人もイスラエル軍によって不当な扱いを受けた経験を持つ。「私の住む難民キャンプで、友人が軍人に理由も告げられないまま連行されそうになった。もちろん私は必死に抵抗した。するとイスラエル兵に「俺はお前を殺すつもりはない。だけど少し教育しなければいけない。」と言われ、足を撃たれた。」と語った。
彼にラーマッラー近郊のアラマリ難民キャンプを案内してもらった。まずここで目を引いたのは、ハマス支持を表明する旗や壁画である。ハマスは、ガザ地区を基盤にしており、ファタハと対立するパレスチナの過激派で、イスラエルの存在を認めていないレジスタンス勢力だ。もちろん日本政府もハマスをテロ組織に認定している。まさかヨルダン川西岸地区でこんなにハマス支持が広がっているとは知らず、衝撃を受けた。
難民キャンプ内の生活環境は非常に劣悪だった。キャンプ内を歩いているとイスラエルにより命を奪われた人々の写真のポスターが街中に張り出されている。その一つの前に立っていた少女に尋ねた。8歳というその少女は笑顔が素敵な子だった。ナセルさんが「このポスターの人に何があったんだ?」と訊くと、少女は、「これは私のお父さん。10日前に殺されたんだ。」と語った。少女によると、10日前の夜、ブルカ(女性ムスリムがつける黒いベール)を被ったユダヤ人男性に、彼女の父は自宅で射殺されたそうだ。ナセルさんも私も思わず言葉を失った。不条理な死が日常化している。
少女と別れ、さらに歩いていると無残に破壊され、有刺鉄線が張られている家を見つけた。その隣に住む女性が語るには、この家に住んでいた息子がイスラエル兵を殺して、その報復として家が壊され、おばあさんが巻き込まれて亡くなったという。そこでナセルさんはいう。「イスラエル兵を殺したこの家の息子は確かに悪い。だけどイスラエルは報復として全く関係のない家族の家を壊しておばあさんを殺した。何もしていないおばあさんが死んだんだ。普通の法律でもイスラム法でも、罪を犯したときはその個人が裁かれる。それは問題ない。だけど全く関係のない人にまで危害を加えるイスラエルのやり方はおかしいだろ?これがパレスチナ人の怒り狂う理由なんだ!」と。
私はいま、「法の支配」が存在しない場所に立っていることに気づき、背筋が冷たくなった。これがパレスチナの現実なのだと改めて知った。そして、彼らが平和的生存を享受していないことを、この道端に普通に落ちている薬きょうが物語っている。
ラーマッラーではパレスチナの政府関係者のもとを訪問した。難民省では、そこの高官の方にお話を伺った。彼は、私が訪問する直前に日本のJICAでの研修から帰国したところだったのだが、イスラエル当局にパスポートを没収されたという。その手続きなどで忙しく、あまりお話を伺えなかった。難民省の彼の部屋にポスターが貼ってあったのだが、これについて尋ねると、「PLO難民省ではナクバの教育をしている。UNRWAの学校ではアメリカの圧力があり、パレスチナの子供たちにイスラエルに都合の悪いナクバを教えられない。その代わりに私たちが教えている。」と語った。
その後、ジャラゾン難民キャンプに向かい、日本のJICAからの援助金の使途を話し合う会議に出席させていただいた。この辺りの所感は後にまわす。
差別の最前線
ラーマッラーを後にしてヘブロンに向かった。パレスチナ自治区内は行政権と警察権をパレスチナが持つA地区、警察権をイスラエル軍が持つB地区、両権限をイスラエル軍が持つC地区がある。ラーマッラーとヘブロンは共にA地区だが、B・C地区を通過するため、パレスチナ人は検問所を通る必要がある。この日も検問所を先頭に長い渋滞が発生していた。50kmほどしか離れていない両都市間の移動に際し、4時間以上かかった。エルサレム在住の日本人の国際協力機関関係者によると、最近、迅速な移送と治療が必要だった重病患者のおばあさんが、長い検問のために亡くなってしまったそうだ。私は暇な学生旅行者だったからよいものの、パレスチナに暮らす人々にとっては深刻な問題になっている。
ヘブロン到着後、道に迷っていると、英語が達者なソーシャルワーカーを名乗る青年が助けてくれて、街を案内してくれることになった。ヘブロンはイスラム教とユダヤ教に共通する預言者、アブラハムの墓廟が存在するためこの一帯にはユダヤ人入植者とパレスチナ人の混住地域がある。この写真はシュハダー通りで撮ったものだ。地上1階部分にはパレスチナ人、上層部分はユダヤ人入植者が住んでいる。入植者が下にごみや卵を投げたり小便をかけたりするため、ネットを設けているそうだ。アブラハムモスク周辺の混住地域ではイスラエル軍によって多数の死傷者が発生しており、シャッター通りになっていた。イスラエルの軍人が、パレスチナ人男性を停止させて所持品を出させて腕を後ろに組ませて尋問していた。「アラブ死ね!」と叫ぶユダヤ人入植者もいた。そこで見た光景は差別そのものだった。ヘブロンを訪ねて初めてパレスチナ問題が「対立」ではなく「抑圧」であることを悟った。
次にベツレヘムに向かう。たまたま泊まった宿は、アイーダ難民キャンプの内側にあった。翌朝の散歩の時に分離壁まで行った。この壁は、イスラエルの文脈では、「テロ対策用フェンス」、パレスチナの文脈では「アパルトヘイトウォール」と呼ばれる。セキュリティの大義名分のもとに非人道的行為のすべてを正当化するという、イスラエルのお家芸の権化といえよう。この壁の目の前に立ち、「安全のため」と言われた時に思考停止してしまう人間の心性を恐ろしく感じた。分離壁をどれだけたくさん築いたとしても、占領という問題の根本が解決されない限り、意味をなさない。むしろ分断の拡大につながり、パレスチナ人の対イスラエル感情の悪化に繋がる。日本でもそれを感じることはあったが、イスラエルでも思考の惰性が蔓延しているように感じた。この壁に描かれているパレスチナ人の平和への思いを胸に刻み、この場を後にした。
今回UNRWAやJICA、NGOの関係者から、さまざまな活動について話を伺った。お話をしていただいた方々は、本当に志が高く、パレスチナの平和について真剣に考えておられる素晴らしい方々だった。特にJICAは日本の国際協力機構であり、日本国民の税金が遠いパレスチナの地で様々な形で役に立っていることを知った。
ただ、ここで考えたことがある。確かに彼らの活動は人道的で素晴らしいことであり、その姿を見ると本当に頭が下がる。困っている人がそこにいる以上、こうした人道支援はこれからも続いていってほしいと思う。しかし、これだけを続けても、パレスチナ問題は解決されない。こうした活動はけが人に例えると応急処置にほかならず、根本的な手術がなされないと永遠に治癒されない。国際社会はパレスチナというけが人の応急処置をしているにとどまり、手術をできないまま70年が経ってしまった。つまり、イスラエルによる占領という根本的原因を解決できないでいるのだ。国際貢献をしているといううわべのスタンスを貫き、根本的な解決に踏み込むことができずに、パレスチナ問題を深刻化させてしまった国際社会の責任は重いのではないかと考えた。その結果、何をもってパレスチナ問題の解決といえるかが難しい境地にまで来てしまった。
短かったが濃いパレスチナ訪問を終え、再びテルアビブの空港に到着し、このポスターを見た。「シオニズムは永遠の理想」とある。アラマリ難民キャンプで出会った少女、無残に破壊された家屋、ヘブロンの差別、ベツレヘムの分離壁。今までに観てきた光景を思い返した自分は、この「理想」が全くの幻想であることを確信した。
パレスチナは、ゼミでの発表のために取材させていただいた臼杵陽・日本女子大学教授の言葉をお借りすると、まさに「世界の構造的矛盾の結節点」となっている場所だった。
歴史的にみても、ナショナリズムに基づく感情は為政者によっていとも簡単に高揚され、扇動され、異民族と認識した対象を排斥する方に向かう。シオニズムという思想も植民地主義的ナショナリズムにほかならない。つまり、一民族には一国家が必要なのだから中東のパレスチナの土地に、ユダヤ人のための国家を創ろうという思想だ。イスラエルという国家の根本にシオニズムがあるのは先述のクネセトの説明の通りだ。ユダヤ教徒という本来人種も居住地も異なる人々が、ヨーロッパで迫害されたことで、本来は「ユダヤ教徒」だったのが「ユダヤ人」化し、近代にはその国家を持とうとする運動「シオニズム」が生まれ、ナチスによるホロコーストを経て、イスラエルが建国された。結果的にヨーロッパキリスト教社会がユダヤ人を差別し迫害したつけを中東のパレスチナが払うことになっている。
先に「嘆きの壁」の写真をご覧になれば分かるように、どう見ても全員の見た目は異なる。エチオピア系と思われる人、中東の人間の顔つきの人、東欧にいそうな人がおり、先祖のディアスポラ先によってその人の見た目が変わる。だが、シオニズムの下に全員がユダヤ人になることに奇妙な感覚を覚える。彼らはユダヤ人としてのアイデンティティを与えられ、パレスチナ人を敵として認識するように幼少のころから教育されて育ってきている。まさに徴兵はその最たる例だと言えよう。主にユダヤ教徒は18歳か19歳になると徴兵され、最前線、即ち占領地パレスチナに飛ばされ、常に緊張状態の中、銃を構えてパレスチナ人を抑圧している。
パレスチナ人はそもそもアラブ人である。だが、中東戦争勃発後、メディアの後押しもあり、「パレスチナに住むアラブ人」が「パレスチナ人」に変容した。パレスチナ政府高官に取材した際にも、彼らには、パレスチナ人としての自意識を強く実感した。彼らはUNRWAの学校では教えられないナクバ(1948年の第一次中東戦争のパレスチナ側の呼び名)を教えていると言っていた。確かに歴史には多面性がある。だからパレスチナ側から見た歴史を教育するのも重要だ。だが、それに終始してしまうとイスラエル人の一般市民と接する機会がほとんどないパレスチナの子供たちにイスラエルに対する恐怖を植え付けてしまい、解決の阻害につながっているのではないか。それも西岸で見たハマス支持の広がりの背景の一つだろう。
その結果として一番明快なのはイスラエル人が右派シオニストを支持している一方で、パレスチナではハマスが支持を広げていることだろう。双方ともが、民主的なプロセスを経て排外的思想を持った代表を選んでしまっていることに、分断を感じる。
そもそもこの地域にナショナリズムの波が押し寄せる前、即ち近代のオスマン帝国下では平和に共存していた。しかし、今は周知のような状態になった。つまり、イスラエルもパレスチナも国民国家の波に飲まれた犠牲者ということができるのではないだろうか。既存の国民国家という枠を超えた議論が必要なのではないかと思うのだ。国民国家の維持、民族の生存圏のためにかけがえのないたくさんの命を犠牲にする価値があるのか、今一度問いたい。
今回、小学生の時に芽生えた問題意識に基づき、こだわりの現場を初めて訪れたが、最初は1週間の滞在期間中に何か1つでもこの問題の解決の糸口が見つかればいいなと軽く考えていた。例えば、日韓の歴史問題のように、相互不信が問題の根本にあり、それを取り除くことで平和は訪れるのではないかと考えていた。だが、それは非常に拙速な考えだった。パレスチナの現実は想像していたよりもはるかに深刻で、絶望しかない世界が広がっていた。そもそも、イスラエルによるパレスチナに対する抑圧は現在進行形で起こっている点で、日韓の問題と決定的に異なる。アラマリ難民キャンプで出会った少女(父親を10日前に殺された)は、イスラエルに対する恐怖と憎悪を生涯抱き続けるだろう。やはり、「占領」という根本的な問題を解決し、国民国家そしてナショナリズムを批判的に検証し、寛容の精神を醸成できる構造を世界的に模索し構築していかない限り、パレスチナ問題を解決することは永遠にできないだろう。
追記——私自身について
最後に自分自身について述べたい。今の世界には私のようないわゆるハーフ、そして混血が当然のようにどこにでもいる。私は自分自身がいったい何者なのかというアイデンティティの崩壊を何度も経験してきた。しかし、だからこそ確信していることがある。それは、アイデンティティは所与のものではなく、単なる思い込みに過ぎないということである。これまでにも「自分は何者か」と自問してきたが、納得できる明確な答えは結局出ていない。もし父親がパキスタンにとどまったままで、パキスタン人と結婚していたら、私はパキスタン人いう確固たるアイデンティティを持つことができたかもしれない。そして、ウルドゥー語を勉強しモスクでお祈りを捧げる生活をしていたことだろう。同様に両親ともに日本人だったなら、いじめられることなく普通に育ち、自分が日本人だという事実に対し批判的に考えることなどなかったことだろう。また、仮に両親にメキシコで産み落とされ、両親の顔を見ないまま育っていたら、自分はスペイン語を話し、タコスを食べ、メキシコ人と認識していたかもしれない(私はよくメキシコ人と間違われる)。
結局、自分が何者になるかは偶然の問題なのではないか。「自分は何者であるか」というアイデンティティを持たなければならないという要請、即ち国民国家下のナショナリズムによって、国に対する帰属意識を植え付けられているのではないか。ナショナリズムを根拠とする国民国家の下では、「民族」という言葉を使って自他を区別し、既成の国家の維持のためにことさら民族性を昂揚させ、幼少のころから体にしみこむように教育することで、民族を所与のものとして受け入れることが常態化していく。民族という概念に対して批判的になり得る人間はそう多くないだろう。そうした批判的思考の欠如、思考の惰性が、パレスチナのような悲劇を生みだしているのではないか。その象徴がまさに分離壁なのではないだろうか。