
2010 年は作曲家グスタフ・マーラーの生誕150周年である。11カ月ぶりの 「音楽よもや話」 は、これについて書こう。
超多忙な日程の合間をぬうようにして、ブルックナーの演奏会【注】のほかに、マーラーのそれにも通った。第3番ニ短調(3月31日、エリアフ・インバル指揮・東京都交響楽団、東京文化会館)、第9番ニ長調(4月10日、ヘルベルト・ブロムシュテット指揮・NHK交響楽団、NHKホール)、第2番ハ短調「復活」(6月16日、インバル指揮・東京都交響楽団、サントリーホール)。インバルのマーラーは、かつてフランクフルト放送交響楽団との生演奏を聴いているので、都響との組み合わせはある程度期待して臨んだが、予想を超えるすばらしい演奏だった。一方、ブロムシュテットの演奏は堅実なもので、第4楽章の最後のppppが消えても拍手が起きない、長い至福の時を体感できた。すぐに「ブラボー!」と叫ぶ困った輩がいるが、この時はそんな心配も無用なほどの静寂が支配した。
なお、個人的なことで恐縮だが、このマーラー「第9」の演奏会は、私にとって一生忘れられないものとなった。18時に演奏が始まり、第4楽章のアダージョ(Sehr langsam und noch zurueckhaltend) の途中、19時15分、娘が孫を出産したのである。演奏会終了後、NHKホールを出て携帯の電源を入れると、そのことを知らせるメールが届いていた。受信時間とメールの内容から、出産はアダージョに入ってすぐのあたりとわかった。 青春時代の忘れられないマーラー「第9」体験は、高校2年の1970年、レナード・バーンスタイン指揮・ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団の演奏会(追記)だったが、今回の体験はそれとはまた別の、大事な記憶となった。
この8月、マーラーの誕生日(7月7日)を意識して、仕事場で、交響曲全集を3日間連続して聴き通した。全集はいろいろな指揮者で持っているし、 父が残したレコードやカセットテープも魅力的だったが 、今回はCD版の全集のなかから、クラウス・テンシュテット指揮ロンドン交響楽団のものを選んだ。
ちなみに、ベルリンでのテンシュテットとの「一期一会」は忘れがたい。 1991年5月19日(日)午後8時 。旧東ベルリンのシャウシュピールハウス(現在のコンツェルトハウス)で、ベルリンフィルとの第6番イ短調「悲劇的」を聴いた。 以前にも書いたが 、鳥肌がたつ演奏だった。咽頭癌を発病し、古巣ベルリンに戻り、最初の演奏会だった。その後まもなく死去するが、その夜の第6番第1楽章の「第一音」(Einsatz)には、 全人生をかけたような迫力があった 。冒頭の写真は、19年前のプログラムとチケットである。 ベルリン各紙(Berliner Zeitung,Tagesspiegel) の音楽批評欄でも大変高い評価を得ていた 。
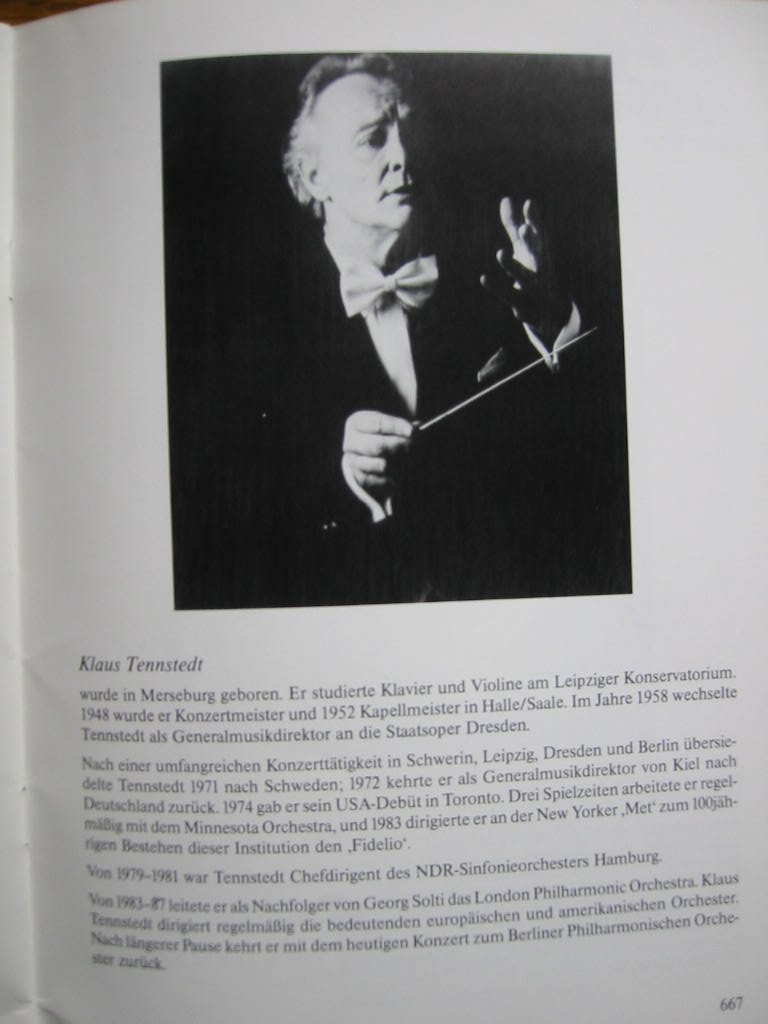
そのテンシュテットがロンドン響を振ったCDの演奏時間は、第1番ニ長調「巨人」53分47秒、第2番ハ短調「復活」88分37秒、第3番ニ短調97分18秒、第4番ト長調54分45秒、第5番嬰ハ短調75分9秒、第6番イ短調「悲劇的」86分58秒、第7番ホ短調「夜の歌」82分26秒、第8番変ホ長調「千人の交響曲」79分7秒、第9番ニ長調85分34秒、第1楽章しかない第10番嬰ヘ長調は28分4秒。トータル12時間13分45秒だった。夏休みだからこその醍醐味である。毎日、朝昼晩ビフテキを3日間食べ続けたような感覚になった。しばらくは聴く気がおきなかった。
マーラーという作曲家は、世紀末の作曲家と言われている。彼が生きたウィーンの世紀末は、現代との間にさまざまな相似を見て取ることができる。社会体制の変動期であり、とりわけ当時の芸術運動の流れは、ある種の「文化戦争」の様相を呈していた(渡辺裕『文化史のなかのマーラー』筑摩書房、1990年参照)。ショーペンハウアーやニーチェの思想もその音楽の奥深くに沈殿している。フロイトとの関わりも一方ならず、マーラーの音楽は「精神分析的な音楽」と言われている。だから、はまり過ぎると危ない。世紀末の共通した「時代の空気」を体現した音楽という面が、20世紀末から21世紀にかけて多くのファンを獲得してきた所以だろう。
彼の交響曲の特徴は、桜井健二によれば、4つある(桜井健二『マーラー・私の時代が来た』(二見書房、1988年参照)。 第1に、矛盾する要素が混然として共存していること。音楽形式の「不均斉」を通じた独創性である。 第2に、多様性をもった音楽表現のために必要とされる長大な演奏時間である。とにかく長い。聴く人には冷静な鑑賞力が求められる。マーラーが書き残した全交響曲の小節数は、21333小節にも達する。第3に、ドラマ性と連続性である。ある交響曲で使われた主題が、別の交響曲で変形して登場し、まったく予期せぬ意外な展開となって「聴く人の足をすくうことさえある」。第4の特徴は、全体を通じて「恐ろしいほどの自己反復」が見られることだ。交響曲以外の歌曲作品(全46曲)にまたがる、創作上の執拗な反復である。歌曲集「さすらう若人の歌」は第1交響曲にそのまま使われ、歌曲集「子供の不思議な角笛」は第2交響曲を筆頭に、他の交響曲にもさまざまな形で登場する。
そのマーラーが中国で人気だという、22年前の新聞切り抜きが、本の間にはさみこんであるのを見つけた。作家・辻井喬氏の「現代中国とマーラー」というエッセーである(『北海道新聞』1988年5月20日付夕刊・文化欄)。茶に変色した切り抜きを読んでみて、さすがに、辻井氏のリアルで鋭い指摘に驚嘆した。
このエッセーは、社会主義のもとで近代化に向かって進み始めた中国で、若者たちがマーラーへの関心を高めているのは「意外な感じを与える」という指摘から始まる。マーラーの常識的理解では、近代が成熟していって、爛熟期に入ろうとする時代のロマン主義なのだから、と。「中国の若者達が、どんな入り口からどのようにしてマーラーの世界に入っていたのかは分からない。たしか少し前には“子供の不思議な造反”〔辻井氏は「文化大革命」のことを皮肉っている〕があって、ある種の権力が彼等を後押ししていたために惨めな混乱が生じた」と。
実は、このエッセーが書かれた1988年は、学生たちを中心に民主化を求める声が高まっていた時期だった。「天安門事件」が起きる1年ほど前のことである。こうした中国の「時代の空気」と、若者たちがマーラーに向かうのとは無関係ではないだろう。辻井氏はマーラー音楽の特徴を簡潔に要約しつつ、「中国の若者に、いま、なぜマーラーなのか」を問う。そして、結論的にこう述べる。
「〔マーラーの〕長大な響き、多様な色彩のなかに中国の若者達は新しい寛(くつろ)ぎを覚えているのであろうか。少なくとも近代工業化社会への踏み込みが、5000年の歴史の積み重ねに強い変化を与えはじめていることだけは確実なように思われる。もしかすると、痛切な喪失の感情を伴う変化こそ、進歩と呼ばれるものの実体であるのかもしれない」と。
いま読み返してみると、 1年後の「天安門事件」 との絡みで実に興味深い。88年当時の若者たちがマーラーに強い関心を示した時代状況の背後で、「多様な色彩」への憧れを阻止する強烈な時代反動が控えていた。「改革開放政策」を通じた資本主義化と一党独裁政治。本来両立するはずもないものだが、中国は権威主義的システムを総動員してその「共存」を力づくでも確保しようとしたわけである。
マーラー生誕150年の2010年10月。街頭で日本車を引き倒して、それを携帯のカメラで撮影して笑っている学生たちの顔には、「天安門」に集まった学生たちの真剣で引き締まった表情はない。現代中国の若者のなかで、マーラーへの関心が広がっているという話はついぞ聞かない。
【注】私が今年聴いたブルックナーの演奏会は、第8番ハ短調(3月25日、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー指揮・読売日本交響楽団、東京オペラシティ)、第9番ニ短調と「テ・デウム」ハ長調(7月11日、ユベール・スダーン指揮・東京交響楽団、合唱団ほか、サントリーホール)、第7番ホ長調(10月15日、スクロヴァチェフスキー指揮・読売日響、東京芸術劇場)、第6番イ長調(11月29日、エリアフ・インバル指揮・東京都交響楽団、東京文化会館〔予定〕)、第9番ニ短調(2011年3月23日、同)である。
付記:事情により新稿を執筆できません。しばらく「雑談」シリーズや連載原稿の転載など、ストックのアップが続くことをご了承く ださい。