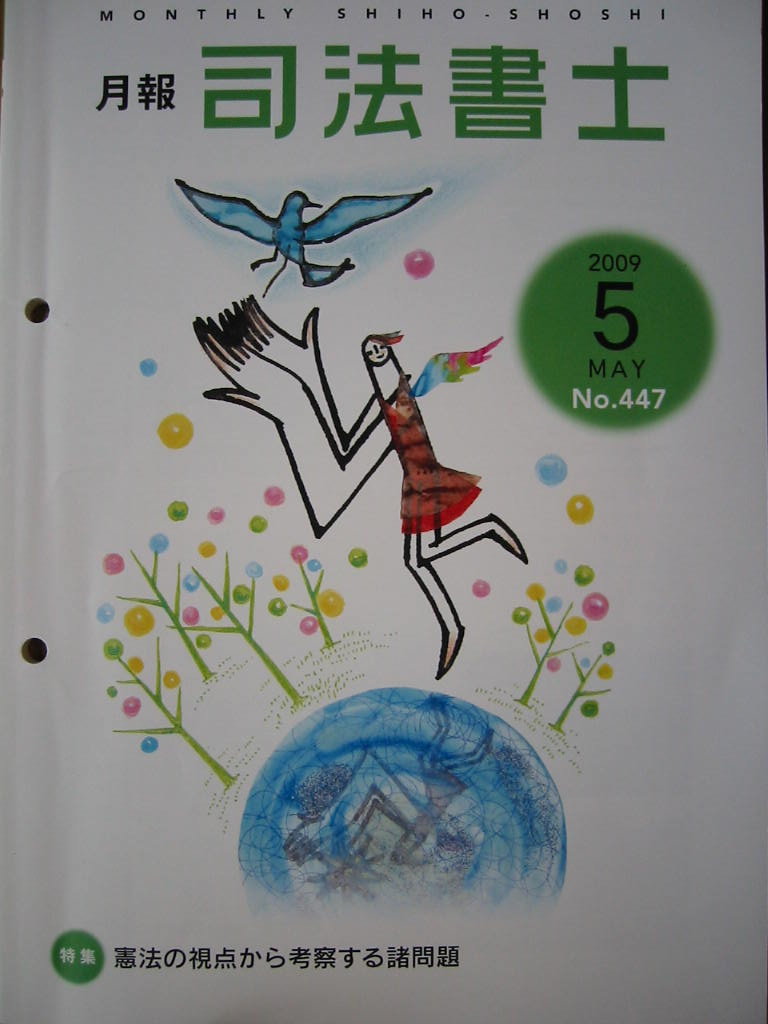
「尖 閣ビデオ」 問題 はその後展開をみせているが、必要な論点は指摘したつもりなので、今回は立ち入らない。 前々回の直言で書いたような事情で 、 既発表原稿をアップすることにより更新に代えることをご了承いただきたい。今回は、日本司法書士会連合会『月報司法書士』2009年5月号(憲法特集)の巻頭に書いた原稿である。
私は日本弁護士連合会(日弁連)をはじめ、北は札幌弁護士会から南は九州弁護士連合会まで、全国各地の弁護士会で講演してきたが、司法書士会で講演する機会も少なくない。この10月9日には、栃木県司法書士会で講演した。学会期間中だったので宇都宮滞在3時間でとんぼ返りしたが、県内各地から集まった司法書士の皆さんに、憲法を活かす視点を熱く語ってきた。 新幹線に飛び乗る前に食べた熱々の宇都宮餃子がおいしかった 。
私と司法書士会との関係は、下記の一文にもあるように、30年以上になる。講演だけでなく、「憲法再入門Ⅰ・Ⅱ」(全23回)を『月報司法書士』に数年にわたり連載したこともある。そういう関係から、2009年5月の憲法記念日に合わせて、当該テーマについて書いたものである。直言で書いた論点や文章も、それを転載するのはやや気が引けるが、このテーマについてコンパクトにまとめたものなので、この機会にご覧いただけたら幸いである。
司法書士と憲法
――何が問われているか――
1 31年前の講演会のこと
「司法書士と憲法」。このテーマに筆者が出会ったのは、今から31年前〔本稿を執筆した2009年から数えて。以下、同じ〕の講演がきっかけだった。 1978年5月17日(水曜)。当時、大学院博士課程院生としてドイツ憲法を研究していた筆者は、東京「中野サンプラザ」で開かれた中野司法書士「水曜会」に、講師として招かれた。当時の手帳を見ると、演題は「憲法と政治の接点――現代民主主義の限界問題について」という何とも硬質なテーマだった。司法書士の方々に、25歳の若造が何を語れるか。いささかどころか、かなり不安だった。それと、「なぜ司法書士が憲法なのか」という素朴な疑問が筆者にはあった。だが、依頼してこられた方は、きっぱりとこうおっしゃった。「私たち司法書士は街の法律家です。司法書士試験の科目に憲法がないので、私たちは独自に憲法について勉強しているのです」と。筆者はその熱意に感銘を受けた。そして、当時研究していたドイツの「自由の敵に自由なし」( 「たたかう民主制」 ) についての理論や制度のこと、1977年「ドイツの秋」(西ドイツ赤軍[RAF] によるテロの嵐)と反テロ立法などについて、ドイツ語文献を並べたレジュメを用意して話した。かなり特殊なテーマであったにもかかわらず、終了後の懇親会にまで議論を持ち越し、多くの方が熱心に質問してきた。以来、何度か憲法について話す機会をいただいた。 1983年、北海道の大学に就職が決まったとき、「水曜会」の方々は、筆者のために「壮行会」を開いてくださった。その時のあたたかい励ましは、今も忘れない。この20代の体験が、その後、筆者と司法書士・司法書士会とのさまざまなご縁が生まれるきっかけとなった。
2 憲法28条とプロ野球選手
「司法書士と憲法」というテーマに関わって、ある重要な動きがあった。それは、2002年の司法書士法改正である。この改正で、司法書士試験の受験科目に「憲法」が加えられたのである(6条2項1号)。2003年の試験から実施されている。択一式で、設問数も少なく、試験全体における比重は決して高いものではない。だが、憲法の試験を受けて司法書士になった人たちは、すでに6期に及んでいる。
「司法書士と憲法」というテーマに関わる重要な変化は、同じ法律改正により、目的規定(1条)が「国民の権利の保全に寄与する」から「国民の権利の保護に寄与する」に改められたことである。「基本的人権の擁護」(弁護士法1 条)に少しでも近づけたいという、司法書士の長年にわたる要求が、「保全」から「保護」への変化の背後にある。簡易裁判所の訴訟代理権を与えられた司法書士もまた、「権利の保護」の担い手としての自覚が求められるようになったわけである。
そうしたなか、2004年9月18日(土曜)は、筆者にとって、とりわけ印象深い日となった。この日、横浜で開催された全国青年司法書士協議会第33回全国研修会で基調講演を行うことになっていた。与えられた演題は「司法書士と人権――司法書士に望まれるもの」。プログラムには、主催者により、「司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権が付与され、職責が加重された今こそ、基本的人権の擁護を自らの使命とし、自らに問い直すべき時ではないでしょうか」というリード文が掲げられていた。この企画全体を通じて、司法書士のあり方をめぐる若手司法書士たちの問題意識と意気込みを感じた。
この全国研修会が筆者の印象に残っていると書いた意味は、実は当日、 「日本プロ野球70年史上初のストライキ」が行われたからである 。
その日午前、渋谷駅でスポーツ新聞全紙を買って、横浜行き電車に乗り込んだ。各紙一面には、およそスポーツ紙の印刷工程では使われることのない「ストライキ」という巨大見出しがおどっていた。乗客の視線をいっぱいに浴びながら、持参したハサミでスポーツ紙の切り抜き作業をやった。会場に到着するや、予定していた講演内容を変更。「プロ野球選手とストライキ」というテーマから語りはじめた。まさに、憲法28条の団結権、団体交渉権、団体行動権(ストライキ権)の「労働三権」とプロ野球選手という、私も考えたことのなかった組み合わせは、実に興味深いものだった。
「たかが選手」(渡辺恒雄・巨人オーナーの言葉)たちによって組織される「労働組合日本プロ野球選手会」は、1985年、東京地方労働委員会で労働組合としての資格認定を受けた。一、二軍の選手全員が加盟している。組織率100%。会長(当時はヤクルトの古田敦也)の信頼度も抜群だった。もし、団体交渉に応じなければ、不当労働行為となる(労働組合法7条2項)。「たかが」という侮辱的態度で臨めば、団交誠実応諾義務違反となる。正当なストに対して損害賠償を請求することはできない(同法8条)。一人ひとりの選手の声は小さくても、自らの権利を守るために団結したとき、それは法的に保障された「力」となる。選手会が日本プロ野球組織(NPB=日本プロ野球機構)に対して団体交渉権をもつことは、選手会が行った仮処分申し立てに対して、裁判所もこれを認めた(東京地裁2004年9月3日決定、東京高裁同9月8日決定)。
この時、焦点となっていたのは球団合併問題や新球団の参入問題だった。これらの問題は経営事項であり、組合との団体交渉を義務づけられる事項ではないという主張が野球機構側からなされた。「違法スト」だとして損害賠償を起こす根拠にもされた。だが、野球協約79条では、各球団の支配下選手は原則70名までに制限されている。2つの球団が合併すれば、一球団分の選手が契約解除になる可能性が高い。球団合併凍結や必要な措置を協議・検討するように求めることは、選手の労働条件と密接不可分な関係にあり、ストライキ要求としては決して不当ではない。先の東京高裁決定も、球団合併について「組合員の労働条件に関わる部分は、義務的団体交渉事項に該当する」と判断していた。経営側が球団合併問題を、選手やファンをないがしろにして唐突に決めようとしたところに今回の問題の発端があった。球団合併を交渉事項にのせて、条件闘争に持ち込んだ古田会長の手腕は見事だった。日頃ストライク(strike)を狙う投手たちも、このストライキ(strike)に参加した。スター選手を含めて、すべての選手が一致団結してストを貫徹した。他方、ファンサービスとしてサイン会などをやったことが、このストへのファンの支持を高めることにもつながった。
9月23日、日本プロ野球組織(NPB)と労働組合日本プロ野球選手会は、来季の新規球団参入に向けて、7項目の合意書に調印した。その結果、9月25~6日に予定されていたストは中止された。
経営側の狙いは、当時の「構造改革」的手法を野球界に応用して、球団の削減をはかろうとするものだった。だが、2つの球団を合併すれば、自動的にファンが一つになるわけではない。球団の削減はファンの減少につながる可能性もある。先の見えないプロ野球危機のなか、このストライキがもたらした影響は決して小さくない。経営側から、「ファンの考えを無視して野球界は動かない、と痛感した。いいチャンスをいただいた」(阪神社長)という声も出てきた。
球団問題を含めて、さまざまな困難で複雑な問題は残ったが、「日本プロ野球史上初のストライキ」の効果は、選手にもファンにも、そして経営者にも、プロ野球の原点を知らしめる意味があったといえるだろう。「たかが選手」が投げたボールは、すがすがしいストライクだった……。 5年前の講演の前半は、このような話だった。
3 「職業としての司法書士」――多様な活動の可能性
この全国研修会に参加していた神奈川県のK氏は、その翌月から行動を開始した。筆者の話を聞いて、司法書士として何かできることはないか、と真剣に考えた末だった。K氏は、自分の事務所がある市内の公園や駅地下道などにいるホームレスたちと語り合うことから始めた。ホームレス支援のボランティア団体と協力しての相談活動になっていく。生活保護の申請をすすめたり、さまざまな支援の形が生まれていった。多重債務を抱えたホームレスが多いことにも気づいた。借金のために家族を捨てて、逃げてきた人も少なくない。K氏はそうしたホームレスの相談活動を続けるなかで、自己破産の手続きをしたり、あるいは過払い問題を解決して、生活を建て直す方向にもっていく手助けもしてきた。K氏が解決した過払い問題は10件以上。なかには数百万単位の過払いもあったという。
「多重債務者を減らせば、ホームレスを減らせる」。これは重要な視点だと思う。こうした活動をしている司法書士は決して多くはないが、ホームレスの自立のための法律支援の活動は、司法書士の新たな可能性を感じさせる試みといえよう。
2005年からは、若手司法書士が中心となって、「生活保護ホットライン」も全国的に始まった。弁護士団体は従来から行っているが、司法書士もこうした活動に加わってきたことは大変頼もしいことである。
また、当番弁護士制度に加えて、司法書士会が「当番司法書士」の活動も始めている(静岡県司法書士会O氏のブログ参照)。会社設立から未成年後見、破産、アパート明け渡し、ヤミ金、相続など、多様な相談が寄せられるという。
さらに2008年秋の金融・経済危機以降、「派遣切り」という言葉に象徴的に示されるような、雇用形態の不安定な人々の問題が深刻化している。非正規雇用者に対する権利保護を格段に高める必要がある。少なくとも登録型派遣の禁止は不可欠である。安定した職をどう確保していくか。「食の安全」だけでなく、 「職の安全」も求められている 。憲法27条(勤労の権利)を基礎に置いた新たな規制が求められる所以である。派遣切りにあった人々に対する支援活動には、司法書士も参加している。
また、地方、医療(特に小児科、産婦人科、救急医療)、福祉といった、「構造改革」で最もダメージを受けた分野の「復興」も緊急の課題である。憲法25条の存在意義はますます高まっているといえよう。
日本の津々浦々で、 「構造改革の荒野」 からの「復興」のため、司法書士に対する社会的要請はますます増えていくだろう。
他方、「職業としての司法書士」という面からみれば、司法書士として収入を得て、生活を安定させることももちろん重要である。日々の業務をきちんとこなし、依頼者の信頼を得る。これは司法書士であることの前提であろう。同時に、「職業として」(als Beruf) というとき、“Beruf”という言葉には「使命」という意味も含まれている。マックス・ウェバーが『職業としての政治』(脇圭平訳、岩波文庫)で喝破したように、権力を本質的属性とする政治の実践者たちが備えていなければならない資質や覚悟というものがある。司法書士が「権利の保護」のための活動を創造的・積極的に展開していくという場合、そこには同じような意味での“Beruf”があるのではないだろうか。
4 そもそも憲法とは何か――「疑の技」
日頃、多くの司法書士にとって、憲法は遠い存在かもしれない。5月3日前後の雑誌特集(本誌も同様)を読む程度というのも正直なところだろう。だが、ちょっと立ちどまって、憲法それ自体についての認識を深めることも大切だろう。
憲法には、歴史上のさまざまな経験と失敗の蓄積の上に、そこから引き出される一定の教訓が、ある程度体系的に、抽象的な文言を駆使して表現されたものという一面がある。そこには、本質的に「疑の技」が仕込まれている、と筆者は考えている。この世に「よい政府」というものは決して存在しないから、 「疑の一字を胸間に存し、全く政府を信ずることなきのみ」 。「東洋大日本国国憲案」を起草した、南国土佐の自由民権運動の理論家、植木枝盛の言葉である(『植木枝盛撰集』岩波文庫)。
「よい政府」、つまり「よい権力者」は存在しない。アメリカ建国の父、トーマス・ジェファーソンがいうように、信頼は常に「専制の親」であるから、猜疑心を持ち続けることが大事なのである。逆にいえば、市民の「疑いの眼差し」に晒されている限り、政治権力は暴走と堕落を免れる可能性が高くなる。つまり「よい政府」は存在しないが、それに接近することはできる。そのための最良の方法は、権力者が市民の猜疑心に晒され続ける仕組みが安定的に存在することである。
人間は誤りをおかし、それを忘れる。そしてまた誤りを繰り返す。だから、過ちをおかしても、修正がきくようにしておくこと、あるいは、できるだけ誤りをおかさないように、さまざまな工夫を凝らすこと、さらには、誤りが起きた場合への対応・復旧策をあらかじめ準備しておくことなどが求められる。憲法というのは、そうした役回りを果たしているとはいえまいか。
その点、ヒトラーとスターリンの暴虐を体験した戦後(西)ドイツは、憲法(基本法という)のなかに、 それらの教訓を徹底して(ある意味では過剰なまでに)書き込んでいる 。 直接民主制への否定的評価、大統領制の形式化 、 内閣不信任・議会解散の難易化 、 「自由の敵に自由なし」の「たたかう民主制」 の採用、等々である。
ドイツにはないが、大統領制を採用する国々にみられる、より一般的なものを一つ挙げるとすれば、 それは「三選禁止」条項だろう 。大統領任期を2期までとするという制度設計について、「なぜ三期はいけないのか」と問われれば、憲法は直接的な答えを用意してくれない。ただ、長期政権は腐敗するという経験知をもとに生み出された工夫であるということはできよう。
「権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」(アクトン卿)という言葉通り、トップの任期を定めない国の最終的な到達点は「世襲」しかない。「人気があっても任期で辞める」。この原則を破る国々が、近年増えている。いずれにおいても国民投票で圧倒的な支持を受けているからやっかいである。ベラルーシ(白ロシア)や、最近では南米ベネズエラやボリビアなどで、国民投票により、大統領の三選禁止条項が廃止されている。直近では、2009年3月18日、旧ソ連の産油国、アゼルバイジャンで国民投票が行われ、9割の国民の支持で、大統領の三選禁止条項が廃止された。これにより、アリエフ大統領は「終身大統領」となる道が開けたという。
憲法というのは、誤りをおかす可能性があり、かつ「忘れる」という人間の本性を熟知した上で、さまざまな「過ち」や「誤り」を体系的に整理・分類して、権力担当者に対してそれらの「記憶」をバックに「命令」として突きつけたものといえる。市民に対しても、常に「記憶」を呼び起こすよう求めている。
「疑の技」を発揮させる上で大切なことは、市民が「忘れない」(想起する、心に刻む、erinnern)ことだろう。「大衆の受容能力は非常に限られており、理解力は小さいが、そのかわりに忘却力は大きい」。これは、独裁者アドルフ・ヒトラーの『わが闘争』にある文章である(平野一郎・将積茂訳〔角川文庫〕上巻)。 「忘却力」は原文では“Vergesslichkeit”となっている 。辞書には「健忘(症)」「忘れっぽさ」とある。ナチスが行ったような「宣伝」に乗せられないためにも、「忘れない」ということに特別の努力が求められる所以である。
憲法12条が、「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と定めているのは、そのためである。憲法とは、人間の本性や習性を十分に踏まえた、「記憶引き出し装置」の役回りも演じている。
市民は、素朴な「疑」の心を大切にして、常に問い続けること。そうすれば、「偽装」を見抜く知恵と「技」を磨くことができる。司法書士の創造的な活動もまた、このような憲法の役割を十分踏まえた上で行われる必要があるだろう。
(『月報司法書士』〔日本司法書士会連合会発行〕2009年5月号2~6頁所収)