
憲法記念日に「防御的民主制(たたかう民主制)」の強調
今年のドイツの「憲法記念日」の特徴として、1849年のフランクフルト憲法175周年との歴史的連関など、「基本法75年」をめぐるポジティヴな側面についてまず論じた。もう一つの特徴は、基本法を「防御」する必要性の強調である。世界的な傾向として、ポピュリズムや極右の台頭が懸念され、EU議会選挙(6月9日)やドイツの3つの州議会議員選挙(特に9月1日のチューリンゲン州が危うい(Björn Höcke 下記の写真参照))での極右政党の躍進がかなりの確度で予想されている。冒頭左の写真は、週刊誌『シュピーゲル』の表紙(Der Spiegel, Nr.21 vom 17.5.2024)。ドイツ国旗の背後からナチスのハーケンクロイツが浮き出てくる象徴的構図である。特集タイトルは「歴史の回帰。連邦共和国の75年、何も学ばなかったのか?」と非常に厳しいテーマ設定で、「ドイツは時の試練に耐えてきたが、極右過激主義やユダヤ人憎悪が克服されたと考えたことは間違いだった」として、最近の傾向について分析を加えている。ただ、反ユダヤ主義を批判する脈絡で、イスラエル批判を批判する傾きが出てくるのは悩ましいところである。
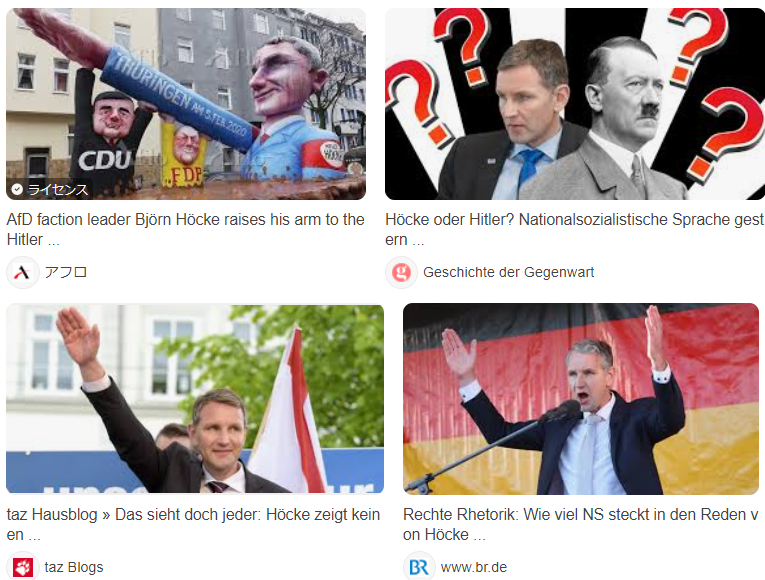
「たたかう民主制」の本質と価値
この点、政治教育センター発行のAus Politik und Zeitgeschichte vom 24.2.2024, In guter Verfassung?)の特集が注目される。その序文(S.3)にこうある。
「…これまで基本法制定の記念日は、自由民主主義的な自己肯定感を讃えるものであった。1949年5月23日に公布された憲法は、ドイツ史における文明的・憲法的な里程標(マイルストーン)として当然評価される。…「暫定的な」基本法が成立した当時は、大きな懐疑的な目で見られ、基本的な改正が繰り返し求められたにもかかわらず、この75年間は幸運の連続であり、世界中の新たな民主主義諸国のモデルであることが証明された。
しかし、今年の祝典には影が差している。右派ポピュリズムの高まり、社会の分極化、フェイク情報操作、外交政策的危機などに直面し、世論の焦点はドイツ第2民主制のサクセスストーリーよりも、その「防御的」要素の活性化に置かれている。議論されているのは、基本法のさらなる民主化の可能性ではなく、政党の禁止や基本権の剥奪に関する問題である。…」
かつて市民社会は、緊急事態法や政党禁止、過激派令などを、開かれた社会の自由を制限するものとして、憲法保護の乱用を危惧していたが、現在では、利用可能な法的救済手段として利用することを求める声が高まっているという。90年代から「極右」シフトへの転換が見られるが(直言「極右政党の違憲訴訟と民主主義」参照)、極右政党の「ドイツのための選択肢」(AfD)の禁止(基本法21条2項)が、党派を超えた世論の要請であるだけでなく、個々のAfD幹部の基本権喪失(基本法18条)までも検討されているという(Hacke)。冷戦時代とは大きな違いではあるが、しかし、表現の自由などの事前規制や予防的制約などに関わるため、「例外法」の行使に常に抑制的に対応してきたヘルムート・リッダーの警告を忘れてはならないだろう。
古くても時代遅れではない―75年目の基本法
連邦憲法裁判所裁判官を務めたディーター・グリムの論稿も収録される。タイトルは「古くても時代遅れではない―75年の基本法」(Dieter Grimm, Alt aber nicht veraltet. Das Grundgesetz im 75. Jahr, a.a.O., S.4-10)。ドイツ基本法は「現在施行されているすべての憲法の中でも、最も古い憲法の一つである。現代社会では、「古い」ものより「若い[新しい]」ものが好まれる傾向にあるが、これは憲法には当てはまらないようだ。ここでは、「古い」は「試行錯誤された」と同義である。基本法ほど「試され、テストされた」とよく言われるものはない。…」 グリムはこう述べて、ヒトラーの台頭を防ぐことができなかったヴァイマル憲法の経験に基づいて設計されている基本法は、「反憲法的な試みに対処するために必要な手段を提供している。もしそれが活用されず、体制を変革しようとする政党が政党競争に参加できるのであれば、多くのことは選挙法にかかっている。ポピュリスト政党が議会で過半数を獲得した場合、その計画をどの程度実現できるかは憲法裁判所にかかっている。したがって、基本法を弱体化させたり、麻痺させたり、権威主義的な形に変容させようとする試みに対して、基本法が何も備えていないというわけではない。」「2024年のドイツ連邦共和国はヴァイマルの状況からはほど遠いが、だからといって安心してはならない。警告が必要であるという事実こそが、基本法制定75周年をこれまでと区別するものなのである」(S.9-10)と。 なお、5月26日の旧東チューリンゲン州の地方選挙で、主要政党が得票を減らすなか、極右AfDが8.6%も得票を伸ばし、9月1日の州議会選挙での躍進が危惧されている(議席予測(inSüdthüringen vom 4.10.2023)参照)。だからといって、この政党の禁止を憲法裁判所に提訴するかどうかは別問題であろう。
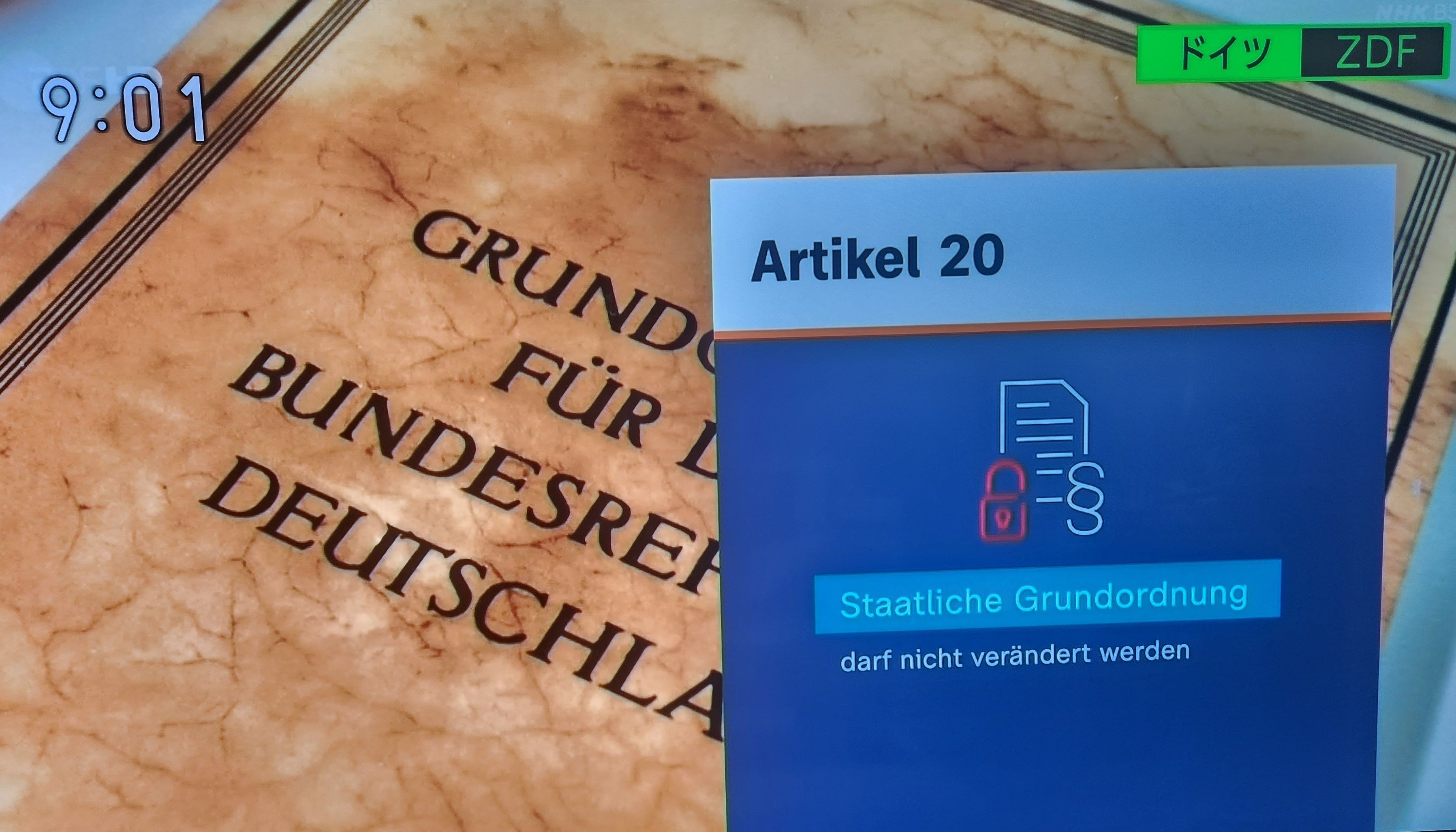
憲法改正の頻度の問題――67回も改正する必要があったのか
ここで、ドイツ基本法改正の頻度について見ておこう。一般に、憲法改正の回数を殊更に問題にして、日本国憲法が一度も改正されていないことを否定的に評価するために、ドイツ基本法の頻繁な改正を持ち出す俗説がある(例えば、直言「46対0でドイツの勝ち?」)。基本法は制定以来75年間に67回改正されている。直近の改正は、2022年12月24日の改正(82条(法律の電子公布に関する但し書きの挿入))である。
連邦議会の調査部門がまとめた文書(『基本法75年――1949年以降の基本法改正』 )は大変便利で、改正頻度や内容の情報も充実している。それによれば、67回の改正により計122カ条が改正の対象となり、同一条文内の追加・修正を加えて237箇所に手が付けられている。大半は連邦と州の関係や国家機関の権限分配などに関わるもので、国民の基本権に関するものは7回で、16の個別改正にとどまる。そのうち特に批判が強いのは3つである。
まず、1968年の第17次改正の「緊急事態憲法」に関連して、電話盗聴の権限が導入されたことである(10条2項)。次に、1993年の第39次改正による16a条の新設である。基本法制定以来、16条は「庇護権」を広範に認めるものとして知られてきたが、難民対策(当時は旧ユーゴ難民)の関係からこれを制限することになった。さらに、1998年の第45次改正。13条の住居の不可侵条項に、組織犯罪対策との関連で室内盗聴(盗聴器の設置)を可能にする3項以下の条文が新設された。
このほか、例えば、1994年の第42次改正では、男女同権と障害者の不利益取扱の禁止が導入され(3条)、また、「自然的生活基盤の保護義務」という国家目標(20a条)が追加された。2000年の第48次改正では12a条が修正されて、女性が連邦軍の戦闘職種に就くことが可能となった。2002年の第50次改正では20a条に「動物保護」という国家目標が追加された。近年では、教育のデジタル化を全国的に推進するため、州の権限になっている教育について、デジタル化を全国一律で行えるように国(連邦)の関与に根拠を与えるため、第63次改正が行われている(詳しくは、直言「教育デジタル化のために憲法改正?―ドイツ基本法第63次改正の迷走」参照)。
改正の頻度を表面的に語るのではなく、改正の中身の問題を考える必要があろう。大前提として、ドイツ基本法は、日本の改憲論議のように「何でもあり」ではない。79条3項によれば、「人間の尊厳」、基本権、連邦国家、民主制、共和制、法治国家、社会国家は改正の対象にならない(「改正限界」)。右上の写真は、5月23日19時のZDFニュース(heute)がこの「改正限界」を図示するのに、国家的基本秩序の改正不可を示す「鍵」のマークを付けているのはうまい表現だと思った。基本法を「建築現場」に例え、その変遷を語る論稿(Im Wandel: Baustelle Grundgesetz, in: Das Parlament vom 11.4.2023)によれば、基本法は146カ条のうち、1949年の制定当初と同じ文言は、現在、半分も残っていないという。「条文の数は200以上に増え、23000語を超えて、現行の基本法の文章は制定当初の2倍以上の長さになっている」。でも、「改正の大半は、政治プロセスと政治主体間の権限配分を微調整することを目的とした国家組織の問題に関するものである」。したがって、連邦の競合的立法権限のカタログを定めた74条ほど頻繁に改正される条文はないという。
ドイツは連邦制をとるので、連邦が専属的に担う事項(例えば、外交事務、通貨、関税、航空交通などが73条に列挙されている)と、連邦だけでなく州も立法できる事項があり、それが74条で、各種法律・法律相談(1号)から大学の入学許可・卒業(33号)までズラーッと列挙されているのである。74条の解釈・運用ではすまないような新たな事項を入れる必要性が出てくると、基本法が改正されてきたわけである。日本国憲法第4章(国会)にそのような条文は存在しない。それぞれの国の憲法の特徴を知れば、日本国憲法が一度も改正されないからといって、頻繁に改正するドイツより劣っていることにはならない。
むしろ67回もの頻繁な改正について批判的意見もある。元連邦憲法裁判所裁判官のグリムは、前述の論稿「古くても時代遅れではない―75年の基本法」のなかでこう述べている。「すべての改正が基本法を改善したわけではない。特に有害だったのは、憲法の機能にふさわしく基本的な記述にとどめず、実際には単純な法律のレベルに位置づけられる細かい規制を基本法に盛り込みすぎた傾向である。その責任は政党にある。政党は、政権交代後に相手側ができるだけ変更しないように、自分たちの関心事をできるだけ憲法レベルで固定化しようとする。このことは、憲法の過多が美学の問題ではなく、民主主義の問題であることを示している。憲法レベルで規制されるものはすべて、民主的プロセスから排除されるのである。…」(Grimm, a.a.O.,S.8)。
傾聴すべき意見といえる。加えて、前述の10条の改正(電話盗聴)や13条の改正(住宅への盗聴器の設置)については、「憲法に違反する憲法改正」というやっかいな議論があることも知っておく必要がある。

ドイツ基本法も「押しつけ憲法」か
ところで、改憲派のいう「押しつけ憲法論」はドイツではどうだろうか。改憲派は日本国憲法を「マッカーサー憲法」というが、日本を占領した連合国軍の最高司令官はマッカーサーだけだった。ドイツは米英仏ソの4カ国分割占領だった。右上の写真は、半ば冗談で作られた、4カ国占領時代のドイツをあらわす国旗のモデル案である(ボン歴史博物館所蔵、2016年8月撮影)。旧西ドイツ地域には米英仏の3人の占領軍政長官がいた(左上の写真、同)。彼らが西側占領地区の11の州首相に対して基本法制定を指示して(「フランクフルト文書」)、基本法制定会議(「議会評議会」)が誕生する。制定から個々の内容に至るまで、軍政長官らの介入・干渉が行われた。特に米軍政長官のクレイ大将は、二院制の採用や緊急権限の制限など、内容に踏み込む細かな指示を8点にもわたって行い、さすがに米国務省からクレームがくるほどだった(直言「基本法は押しつけ憲法か?」)。
日本国憲法の制定過程と比べると、「押しつけ」が外によく見える分、ドイツの方が露骨だったともいえる。だが、これをもって基本法を占領軍の「押しつけ憲法」という人はまずいない。占領下の制憲である以上、当然という認識だろう。この点を掘り下げた森征樹「ドイツ基本法制定過程における「押しつけ」の有無」(『桃山法学』33号(2020年195-242頁)が参考になる。その結びの部分を引用しよう。
「ドイツ基本法も日本国憲法も、その制定過程の現象面においては、ともに占領国による「介入」があった。それを「押しつけ」と捉えて、憲法改正(もしくは自主憲法制定)の根拠としたのが日本の支配層であり、ドイツにおける「押しつけ」論がごくわずかの右派または極右の側からしか唱えられていないことを鑑みると、結局のところ、「押しつけ」を声を大にして叫ぶのは、現行憲法の内容面に不満を持つ層であることが分かる。身も蓋もないことを言えば、憲法が仮に他国によって自国民の自由な意思なく完全な形で「押しつけ」られたとしても、それが憲法の正当性を揺るがすものになるとは思えないのである。憲法とは、その国の統治の仕方を定めるルールであり、その出生がどうであれ、内容を国民が現在支持しているかどうかがすべてなのである。そう考えれば、基本法はおろか、日本国憲法も決してその正当性を「押しつけ」だからと言って否定されなければならない理由にはなりえないのではなかろうか。」
40+35のドイツ基本法75周年
私がドイツ基本法50周年をボンで立ち会ったとき、「40+10」という視点が打ち出されていたことは前述した。今年11月9日は、「ベルリンの壁」崩壊35周年である。したがって、先週の「基本法75周年」は「40+35」という視点で考えることができよう。つまり旧西ドイツ基本法の時代が40年、「壁」崩壊後が35年と、ほとんど相半ばするに至った。ということは、5年後の2029年は「基本法80周年」ということで「40+40」ということになる。各種世論調査を見ても、旧東の人々の基本法への評価は高い。旧東の人々にとって、基本法は旧西ドイツから「押しつけられた憲法」という意識はなくなりつつある(直言「ドイツ基本法70周年の風景」)。
このように見てくると、首相が施政方針演説で、「任期中に憲法改正を実現したい」などといって、それをメディアがそのまま見出しにして垂れ流す異様さを知るべきである。憲法に緊急事態条項を入れることに与党・維新はエネルギーを割いているが、「1.1大震災」から今日で147日になるのに、輪島市で1000戸を超える所帯が未だに断水という緊急事態をどう解決するのか。緊急事態の問題は憲法改正の問題ではなく、これから起きる新たな大水害にも適切に対応できない政治の問題であろう(直言「「危機」における指導者の言葉と所作(その2)―西日本豪雨と「赤坂自民亭」」参照)。

