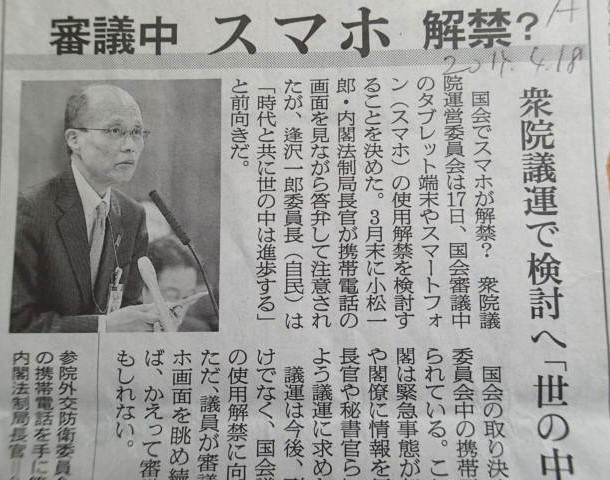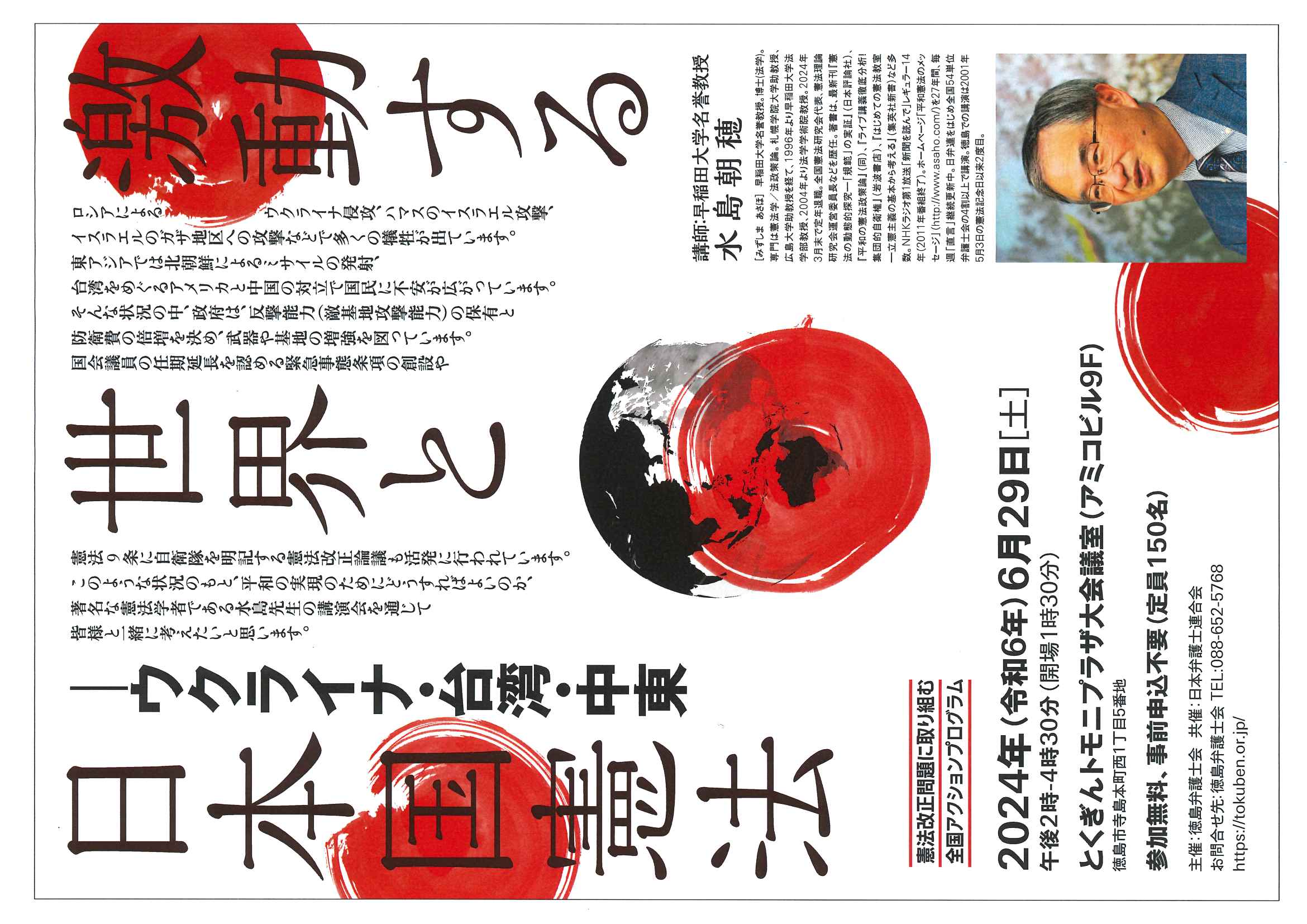
徳島弁護士会で講演
先週末、徳島弁護士会で講演した。2001年の憲法記念日に講演して以来、23年ぶりの徳島だった。講演の翌日、主催者のご配慮で鳴門市ドイツ館(板東俘虜収容所)を再訪した(直言「第九のふるさと」訪問」参照)。「渦の道」も見学した。昨日の午後、帰りの便に乗ろうと徳島空港に着くと、SPが随所に立っている。土産物コーナーでお菓子を探していると、すぐ横に木原稔防衛大臣と三宅伸吾政務官が立っているではないか。2人とも議員バッチを外して目立たなくしているが、政務官はブルーリボンのバッジを付けていたのですぐわかった(ちなみに、不祥事隠蔽疑惑で問題となっている鹿児島県警本部長がこのバッジを付けて答弁しているのには違和感)。4月20日に伊豆諸島の鳥島東方海域で訓練中の海上自衛隊哨戒ヘリSH-60Kの16号機と43号機が接触して墜落。この事故で8人の隊員が死亡したが、43号機が所属する海自小松島基地(第24航空隊)で、4人の隊員の葬送式が行われていた。非公開のため、大臣、政務官の出席について、NHK徳島のニュースは「防衛省関係者」としか伝えていない。事故の背景には、近時の自衛隊任務の拡大のなかで、現場の負担がかなり大きくなっていることもあるようだ。
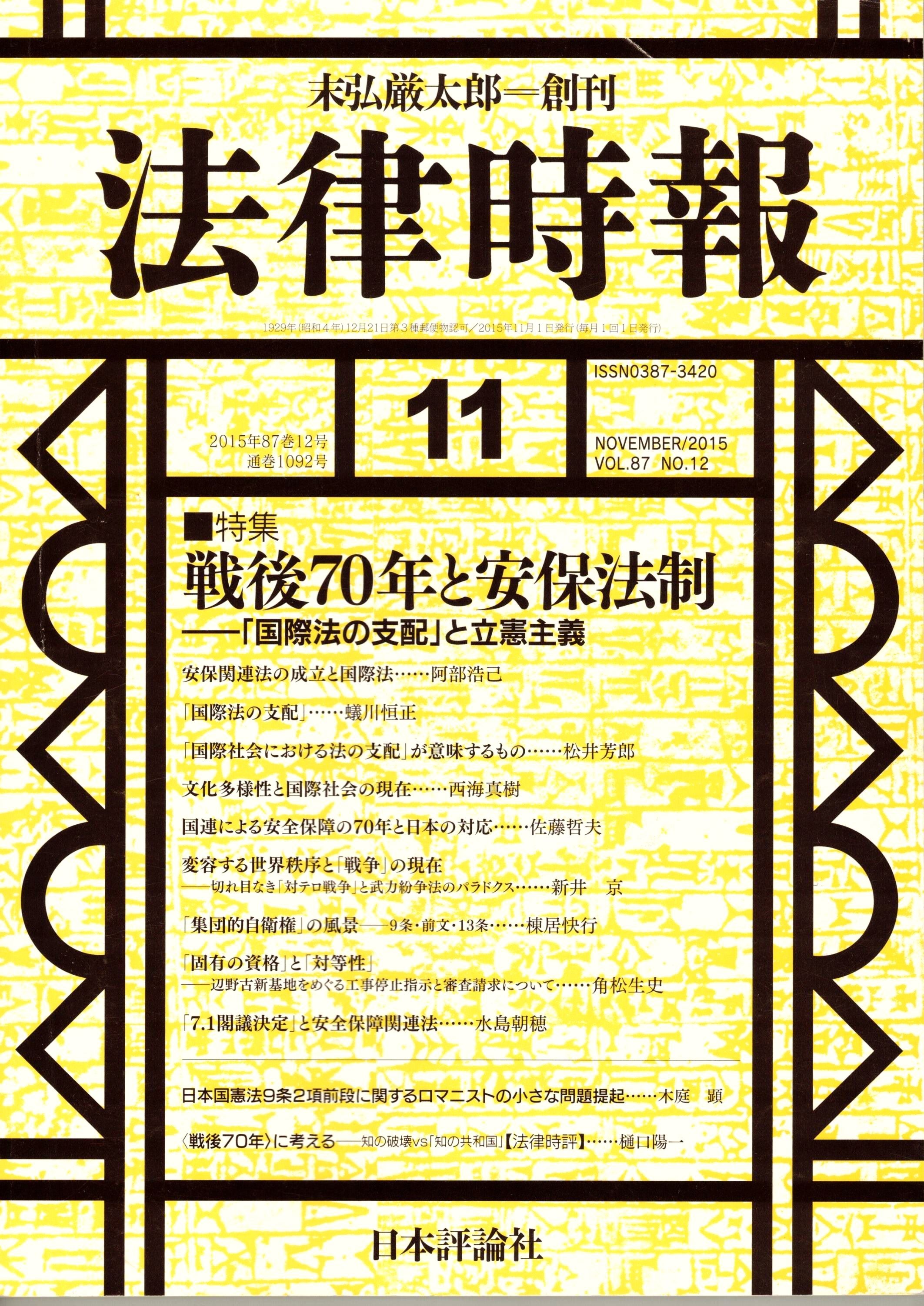
この「7.1閣議決定」による憲法解釈変更前は、「我が国に対する武力行使の着手」がなければ日本は個別的自衛権の行使として武力の行使をすることができなかった。憲法9条が明文改憲されないまま存在していること自体が規範力を発揮し、それを軸として、長年にわたる国会における議論の積み重ねや長沼一審判決の存在が、政府の憲法解釈を変更する際の高いハードルとなってきた。集団的自衛権行使の違憲解釈についても、1954年以来の「自衛力合憲論」を軸とした政府解釈の根幹に関わるため、「7.1閣議決定」まで寸止めで維持されてきた。だが、憲法解釈変更により、「他国に対する武力の行使」を契機とする集団的自衛権行使が認められてしまったため、「我が国に対する武力行使の着手」前から集団的自衛権行使として武力の行使が可能となってしまった(詳しくは、直言「「敵基地攻撃能力=抑止力」という妄想(その2)」とその図を参照)。これは日本の平和にとってきわめて重大な意味をもっていた。それが2015年の安全保障関連法(「平和安全法制」)につながっていくことについて、詳しくは、拙稿「「7.1閣議決定」と安全保障関連法」(『法律時報』87巻12号(2015年)(拙著『平和の憲法政策論』(日本評論社、2017年)所収)を参照されたい。
「7.1閣議決定」に至る手始めは、法制局長官人事だった(直言「「壊された10年」―第2次安倍晋三内閣発足の日に」)。2012年に政権にカムバックした安倍が最初に手をつけたのは、日銀総裁、内閣法制局長官、そしてNHK会長の人事だった。従来の政権に見られない露骨さ、あざとさは、その後も、黒川弘務・東京高検検事長の人事をめぐって、検察庁法や国家公務員法の体系に、閣議決定を使って強引に手を突っ込んでいったことからもわかるだろう(直言「検察庁法改正をめぐる政権の恣意」参照)。
法制局長官人事は、2013年8月、まったく予想外の人選だった。外務官僚である小松一郎前・駐仏大使を長官に任命したのである。小松は集団的自衛権の行使に前向きの人物で、安倍のお気に入りだった。衆院議院運営委員会でスマホを見ながら答弁して、野党委員にたしなめられている(写真は『毎日新聞』2014年4月18日付)。法制局長官という、法の解釈・運用の要となる機関の長にもかかわらず、この軽さは際立っている。
内閣法制局というのは、長官、次長、第1部から第4部までの部長、総務主幹の7人の幹部がいて、長官になる人のコースは、総務主幹から始まり、2部から4部のいずれかの部長を経験し、意見部の第1部長として、政府の憲法解釈を担当してから次長となり、長官となっていく。だから、長官は、次長と第1部長を必ず経験した者がなる。この表をご覧いただきたい(『毎日新聞』2014年9月28日付3面)。これが法制官僚の頂点である内閣法制局長官人事である。安倍が壊したのは、人事を通じて、法制局を政治的に支配することだった(直言「誰が内閣法制局を壊したのか」)。この10年間、内閣法制局の憲法解釈や意見が注目されることは格段に減ってしまった。
ここで思い出すのは、この長官人事について怒っておられた俳優の菅原文太さんのことである。2013年9月29 日、ニッポン放送のラジオ番組「菅原文太日本人の底力」に出演を依頼され、スタジオに入って、挨拶もそこそこに本番となり、開口一番、菅原さんはこう切り出した。「先月(2013年8月)、内閣法制局の長官が小松一郎さんという人に替えられたじゃないですか。彼は外務省出身で、法律家ではない。そんな人が「憲法解釈の変更がおよそ許されないことはないと考えている」という発言をする。そうなると、これはもう出来レースなんじゃないかと思わざるを得ない」と。言葉数は少ないが、一言一言に重みがあり、菅原さんがこの人事について危機感を抱いておられたことが伝わってきた。菅原さんの死後、この怒りは奥様に受け継がれ、年に何度か励ましのメールが届く。なお、「7.1閣議決定」の具体化としての安全保障関連法の制定過程については、拙著『ライブ講義 徹底分析! 集団的自衛権』(岩波書店、2015年)を参照のこと。
民主党政権時代の「政治主導」
内閣法制局への嫌厭は、民主党政権下でも存在した。過度の「政治主導」が強調され、その一環として、国会答弁における政府委員出席の制限も試みられた。直言「なぜ法制局を排除するのか― 歪んだ「政治主導」」でも指摘したように、「官僚が国会審議や議員の活動に口を出すことを禁止し、政治家自身が政策を立案・決定する本来の制度に改め」ることが強調され、行政機関職員と国会議員との接触制限も考えられていた。「内閣法制局廃止法案」まで想定されていた。安倍政権の無法を体験した野党は、政権交代をしても、この「政治主導」や法制局排除をとることはないだろう(と信じたい)。あの「事業仕分け」の愚を繰り返すべきではない。
来週、7月8日は、「7.1閣議決定」を行った安倍晋三が殺害されて2年となる。
【文中敬称略】