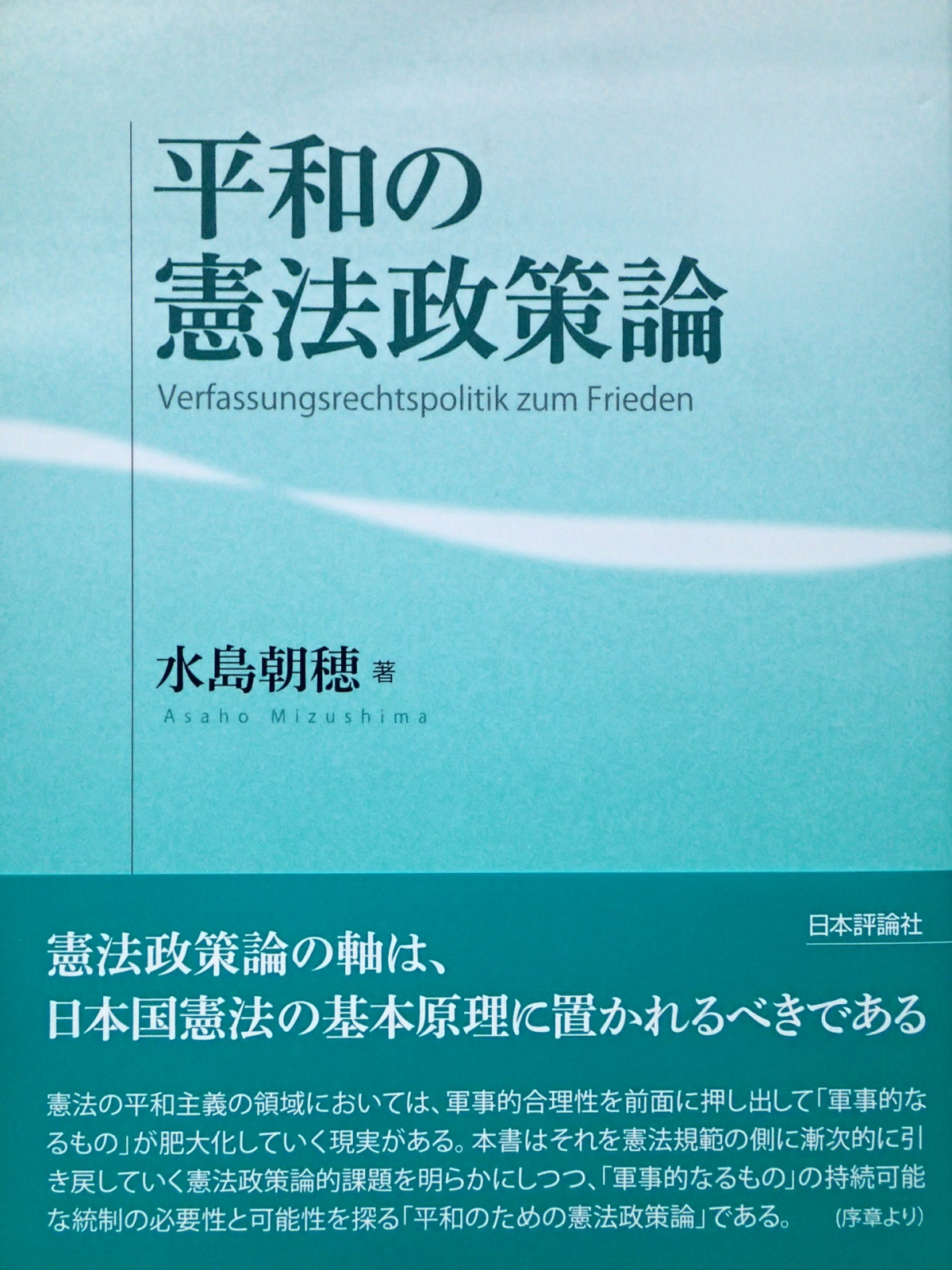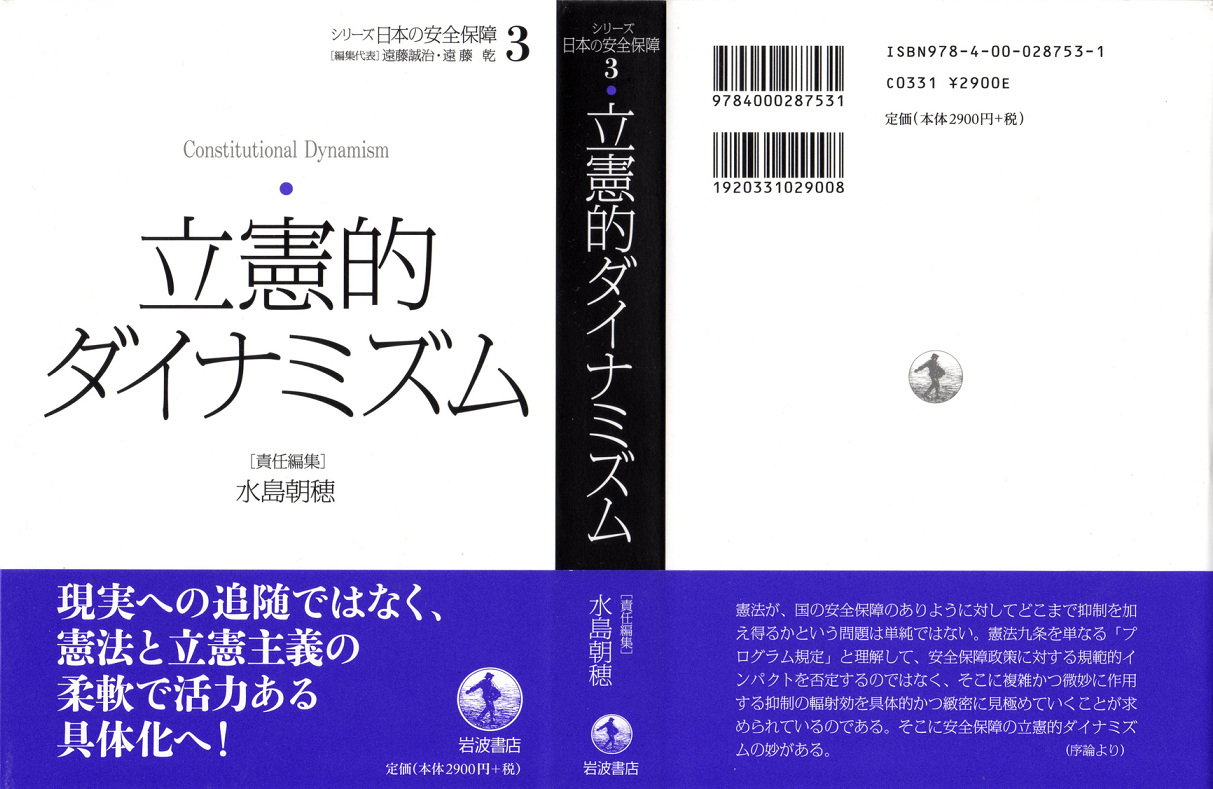多数の小学生を殺害する「力による平和」の現実
この写真は衝撃的である。墓穴が掘られているが、その数、160基あまり。これから掘削する箇所には白い印がついている。『ニューヨーク・タイムズ』3月5日は、イラン南部ミナブのシャジャラ・タイイバ女子小学校を爆撃し、少なくとも女子児童160人を死亡させたのは米軍である可能性が高い、と結論づけた。これは、米国とイスラエルによるイランへの一方的な攻撃の初日に発生した。この攻撃で最高指導者ハメネイ師と多数の政権・軍幹部が殺害された(『産経』を含む各紙2日付はハメネイ「殺害」としたのに、『読売』だけは「死亡」とした。病死でもあるまいに)。『ニューヨーク・タイムズ』はまた、新たに公開された衛星画像や検証済みのソーシャルメディア投稿、位置情報付き動画に基づく分析により、同校が精密攻撃を受けた時刻は、隣接するイラン革命防衛隊(IRGC)所属の海軍基地に対する米軍による複数の攻撃と同時期と結論づけた。過去の画像からは、2016年に校舎が軍事施設から分離され、運動場や児童の壁画など、民間教育施設としての明確な特徴を備えていたことが確認できるという。元米空軍の専門家は、この学校が「標的の誤認」か、あるいは古い情報に基づいて攻撃されたかのいずれかであると述べた。ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、生徒の殺害が国際人道法に対する「重大な違反」を構成すると表明した(以上、写真を含め『南ドイツ新聞』3月6日およびRT0306)。なお、ミナブを所管するホルモズガーン州総局のクレジットの映像がある(動画はここをクリック)。ミナブの女子小学校付近に米軍のトマホークミサイルと見られるものが着弾する様子が映っている。これについて、ワシントンポスト紙3月8日が米軍のミサイルの可能性を示す証拠だと伝え、CNNも3月10日に報じた。映像には着弾後、女性の悲鳴らしきものも入っている。
公海上で国際観艦式参加のイラン艦を撃沈――「静かな死」とは
その下の写真も別の意味で衝撃的である。3月4日、イラン海軍のモッジ型フリゲート艦「デナ」が、インド海軍主催の国際観艦式や多国間合同訓練に参加してからの帰途、米海軍潜水艦から魚雷攻撃を受け、撃沈された。スリランカ南方沖の公海を航行中のことだった。乗組員約180人中、スリランカ海軍によって救助されたのは32人だった。この国際観艦式には、海上自衛隊の護衛艦「ゆうだち」や、ロシア太平洋艦隊のフリゲート艦「マーシャル・シャポシニコフ」も参加していた。米国の艦艇も参加予定だったが、「運用上の理由」からドタキャンしたという(『読売新聞』2月20日)。この段階ですでにイラン攻撃の作戦は動き出していたのかもしれない。
国防長官ピート・ヘグセスは4日の記者会見で、これは「第二次世界大戦以来、魚雷による敵艦の最初の撃沈」であると胸を張った(写真はサンデーモーニング3月8日)。「最初」というのは誤りで、記憶に新しいものとして、1982
年のフォークランド紛争で、英国海軍の原潜が、アルゼンチン海軍の巡洋艦「ベルグラノ」を撃沈して323人が死亡した例がある(直言「「フォークランド戦争」から40年」)。船首を上にして沈んでいくイラン艦の写真。対馬丸をはじめ米潜水艦に撃沈された日本の艦船は1300隻以上といわれる。今回の米潜水艦による撃沈の写真は、それで亡くなった10万以上の人々と重なり、何ともいえない気持ちになった。
ヘグセスはこの記者会見で、イラン艦の撃沈を得々と描写し、これを「静かな死」という意味不明の言葉で表現した。これには驚いた。“Hegseth”“tattoo”でクロス検索すれば、おぞましい写真がたくさんヒットするだろう。インドメディアが報じたのが上の写真である。もともとエルサレム・クロス(Jerusalem cross)は、エルサレム王国(1099年以降)の紋章として用いられていたものである。十字軍に関連するキリスト教の歴史的シンボルだが、近年では極右過激派のなかでも好んで使われている。100人以上の人間を海に沈めて殺す行為を「静かな死」と呼ぶのはまともな神経ではない。トランプ政権を支えるキリスト教福音派の思想と行動とも関連しているのではないか。トランプにせよヘグセスにせよ、イランというイスラム国家を叩きつぶすという十字軍的な香りが漂ってくる。福音派による聖書解釈を、戦争の正当化に最大限利用しているのだろう。ホワイトハウス信仰局長の危うさはすでに述べたが、トランプ2.0のその意味での危うさが、今回のイラン攻撃の背景にあるように思う。

トランプ流の米軍「粛清」とその結果
昨年9月30日、ヘグセスは米軍の高級幹部(将官)を数百人、全世界から一斉にバージニア州の海兵隊基地に集めた(写真は国防総省のHPより)。そもそも司令官クラスの将官全員を、明確な理由も示さずに一斉に招集すること自体異例とされ、軍の運用上も問題があるが、そこでヘグセスが行った演説も異様なものだった。トランプ政権が行ってきた4人の女性の将官解任や黒人のブラウン統合参謀本部議長の解任を擁護し、「肥満の将軍や提督」「ひげを生やすような連中もいらない」として、ジェンダーなどを考慮する「DEI」(多様性・公平性・包摂性)の行き過ぎが米軍にあったと主張するものだった。そして、軍人に「最高の男性基準」を求めた(以下『朝日新聞』2025年10月1日)。トランプも登壇し、1時間を超える大演説を行った。「我々は外敵と変わらない、内側からの(敵による)侵略にさらされている」と主張。サンフランシスコやシカゴなど民主党が強い都市を挙げ、「極左の民主党員に支配されている都市は治安が非常に悪い」と述べるなど、党派色・政治性むき出しの主張を一方的に展開した。性や人種、外見を侮蔑する発言も壇上から激しく行った。将軍たちは複雑な表情でこれを聞いていた。
私はこの「最高レベル会合」(Top-level meeting)こそ、トランプに忠誠を誓わせる場になったのではないかと考えている。もはやトランプやヘグセスを批判する将官たちはいなくなった。かつての「狂犬マティス」やマーク・ミリーのような芯のある将軍たちは米軍から駆逐されたのだろう。実際、制服組トップの統合参謀本部議長のダン・ケインは、経歴はきわめて地味、というより貧弱で、およそそのポストにふさわしい人物ではない。通常、統合参謀本部議長は陸海空軍のトップから選ばれ、空軍ならば空軍総参謀長(大将)を経ることになっていた。ところが、ケインの最終的な役職はCIA軍事副長官で、しかも空軍中将で退役している。なぜ、そんな人物が異例の抜擢人事、超スピード出世で制服組トップになれたのか。それは彼がトランプのお気に入りであることに尽きるだろう。本人は上院の公聴会でこれを否定しているが、トランプは、ケインがMAGA帽をかぶって忠誠を示したと周囲に語っていたという。いずれにせよ、トランプに抵抗した黒人のブラウン議長を任期途中で解任して、その後任につけた以上、MAGA系の将軍であることは確かであろう。ちなみに、自衛隊では陸海空の幕僚長経験者がほぼ順番で統合幕僚長になるが、もし空自補給本部長で退官した人物を、奈良県出身の飲み友達だからといって、統合幕僚長のポストに就けたならば、誰がみても不自然であろう(実際は首相補佐官として問題を起こした)。
さて、このような異例、異様な人事が行われ、忠実な人間だけを残して、あるいは忠犬を新たに投入することによって、2025年中に米軍はトランプ流の「粛清」をされたといえるだろう。誰もトランプやヘグセスに意見具申できなくなった。その結果が、ベネズエラとイランに対する違法、無法な攻撃ということになる。世界一の暴力装置の暴走は止まらない。次はキューバなのかと恐怖さえ感ずる。
この「トランプ忖度」の空気は何だ!
23年前の3月20日、ブッシュ政権はイラクに対する武力行使に踏み切った。「ならず者国家」(Rogue state)と勝手にレッテルを貼って軍事介入する手法である。「イラクの自由作戦」として、フセイン政権を倒すための「自由と民主主義のための軍事介入」とされた。ブッシュ政権は安保理決議を意識したが、当時はドイツもフランスも賛成せず、英国とともにこの戦争に踏み切った。すぐに直言「国際法違反の予防戦争が始まった」をアップして、こう書いた。長いが引用しておく。
「国連安保理決議もない、一見きわめて明白に国連憲章違反の侵略行為である。第一撃はフセイン大統領の殺害を狙ったものだという。超ハイテク兵器を使った、一国の元首の暗殺。ブッシュはこれを「神の意思」という。当初は「9.11テロ」との関係を強調し、次に「大量破壊兵器の脅威」を前面に押し出し、最後には、フセイン体制転覆(体制転換)が直接の目的とされた。米国に都合の悪い政権は、武力で取り替えるという宣言にほかならない。1648年のウェストファリア講和条約は、30年にわたる宗教戦争に終止符を打った。国家が暴力を独占し、国家主権をもつ国民国家が誕生した。それ以降、国民国家の連合体が二度の世界大戦を経て、国際連合という形で登場した。その国連による集団安全保障システムが、ブッシュらによって大きく傷つけられた。ブッシュが昨年9月に出した新戦略に基づく「予防的自衛」「先制自衛」の路線の具体化である。…」と。
上記の「直言」では、「予防的危険防禦」ないし「予防的自衛」(preemptive self defense)について批判する議論を紹介した(イラク戦争20周年の直言「わが歴史グッズの話(51)」も参照)。だが、いま、私たちの眼前で展開しているのは、国際法も国際秩序も、もっといえば、まともな理屈も一切使わない、むきだしの暴力である。
今回、メディアは圧倒的に腰がひけている。テレビのニュース解説や、主要新聞のメインの記事(個々のコラムは別として)は、全体として、まずイランの核開発は許されないと述べてから、米国の攻撃を伝える。イラク戦争の時は、フランスもドイツも米国の武力行使に反対したため、英米によるイラク侵攻になったが、今回米国は、ガザでの虐殺を続けている、真正の「ならず者国家」(Rogue state)イスラエルと組んで、一方的な攻撃を行っている。武力行使禁止原則(国連憲章2条4項)に対する明白な違反を非難すべきところ、まずイランの核開発のことを非難する。イランからの核攻撃が差し迫っているということを具体的に説明できない。国連憲章51条の自衛権行使の要件のことなど、まったく眼中にないようである。国連安保理決議のない「うしろめたさ」(イラク戦争の時はまだあった)も皆無である。そもそもトランプは国連を完全に視野の外に置いている(ガザ「平和評議会」の終身議長!)。
イスラエル軍の国際法の「専門家」は、「戦争の権利」(ius ad bellum)と「戦争中の権利」(ius in bello)という古典的な区別に従ってイランへの攻撃を正当化した。その「論理」は、イスラエルとイランは、2月28日から戦争状態にあるのではなく、「非常に長い年月」にわたり戦争状態にある。したがって、現在の戦争は、両国間の長年にわたる武力紛争の継続である。イランの国家の存立の根拠は、イスラエルの破壊である。したがって、武力行使の合法性(ius ad bellum)はクリアするというものである(『南ドイツ新聞』3月6日より)。自衛権行使の3要件も吹き飛ばす乱暴な解釈だが、その「法的評価は控える」というのが日本政府の対応である。何とも情けない限りである。
「これを国際法違反と認めないのは重大な誤りである」(オーナ・ハサウェイ)
日々のテレビの解説に国際法学者が見当たらない。一方、テレビに出る「専門家」のなかには、スポーツ解説や相場解説者のような乗りの人もいる。そうしたなかで、米国国際法学会の次期会長オーナ・ハサウェイの明確な主張は貴重である(『朝日新聞』2月7日)。ドイツの「憲法ブログ」では、「これを国際法違反と認めないのは重大な誤りである」というタイトルで、ドイツをはじめ欧州諸国が今回の攻撃を国際法違反と断じないことを厳しく批判する。そこで彼女はこう結んでいる。
「トランプ政権がベネズエラに違法介入した後、現在のイラン戦争が始まる前に、私は戦後国際秩序の「大崩壊」についてニューヨーク・タイムズ紙に寄稿した。当時が危険な状況だったなら、今ははるかに悪い。状況が悪化したのは、十数カ国が中東でまたもや拙速かつ違法な戦争に巻き込まれたからだけでなく、国際社会の対応があまりにも弱腰だったためでもある。露骨な無法行為に直面しながら法の支配を擁護する世界の指導者はほとんど見当たらない。これは大きな悲劇であり、この失敗こそが最終的に戦後国際法秩序の終焉を告げるかもしれない」と。
トランプ政権の暴走に対しては、米政府部内にいた人々からもさまざまな異論が出ている。例えば、CIAの分析部門で中東地域を担当していたポール・ピラー(Paul R. Pillar)の論稿「イランとの戦争の驚くほど脆弱な論拠」(The Astonishingly Weak Case for War with Iran)(The National Interest March 2, 2026)は実に興味深い。ピラーは「選択による戦争」(war of choice)という概念を用いてトランプを批判する。侵略を受け、他に現実的な選択肢がない場合の戦争(「不可避の戦争」(war of necessity))とは異なり、「選択の戦争」は、 外交や抑止、封じ込めなど代替手段が存在するなかで、あえて選ばれた戦争のことである。他の政策的選択肢が存在するなかで開始する戦争は、国連憲章の枠組からは正当性を疑われる。ピラーはこの観点から、この対イラン戦争について3点指摘する。
第1に、侵略行為―選択的な攻撃戦争(offensive war of choice)が、あたかも外交的抗議と同程度に無害であるかのように、米国の政策論議において常態化しているように見える点である。侵略は違法であり、国連憲章第2条に違反するとピラーは断定している。
第2に、トランプ政権がイランに対する戦争を正当化する努力を驚くほど怠っている点である。これがイラク戦争との大きな違いとピラーはいう。少なくともブッシュ政権は戦争開始に先立ち、国内外で持続的な宣伝キャンペーンを展開し、大統領演説で説明もしていた。これと対照的に、トランプはほとんど説明していない。虚偽の主張も含む。戦争を正当化しようとする努力の欠如は、おそらくトランプが制約も正当化の必要もなく好き勝手に行動するという傲慢さのまた別の例に過ぎない。あるいはその欠如は、この戦争を正当化する論拠の弱さを反映しているのかもしれない。イランの核計画は昨年6月の米軍の作戦によって完全に破壊されたわけではないものの、深刻な打撃を受けた。それ以来、イランはウラン濃縮を行っておらず、核兵器保有には程遠い状態にあった、と。
第3に、トランプ政権が「時間が迫っている」という不吉な警告を発し、イラン近海に「艦隊」を配備することで、短期間で決着がつく危機のイメージを作り出したことである。だが、その危機はすべて自らが作り出したものに過ぎなかった。トランプが「時間が迫っている」と感じた唯一の点は、議会が戦争権限に関する審議を行う前に、自らの戦争に突入することだった。さらに、イランとの対立を解決するための外交ルートは機能しており、さらなる進展の余地があった(オマーン外相の仲介)、と。
このCIAの分析官の指摘はいちいち納得である。CIAに所属していた人から、「危機はすべて自ら作り出したもの」という言葉を聞くと、これまでもそうだったのではないかと皮肉の一つもいいたくなる。だが、トランプの今回のやり方はやはり悪辣である。この体制内部からの批判は重要である。日本では、この戦争に対するこうした批判が内部からは聞こえてこない。「高市一強」への畏怖と忖度からだろうか。

トランプの暴走への「やましき沈黙」――高市首相は何を約束させられるか
おかしいことは多くの人がわかっていても、「空気」にまけてしまい、ノーということができないことである。「やましき沈黙」がまた繰り返されるのか。直言「ドイツ軍少佐からの白バラ ― 軍人の抗命権・抗命義務」でも書いたように、私は17年前、国際法違反のイラク戦争を開始した米国にドイツ連邦軍が協力する命令を拒否した少佐の話を紹介している(上の写真はその時の講演会)。今回の「イラン戦争」でも、米軍パイロットがイスラエルへのミサイル輸送を拒否するという映像が、公聴会らしき場所で声をあげて拘束される女性軍人(空軍ではない)の姿とともにSNSに流れているが、まだメディアでは報道されていない。
その一方で、首相の高市早苗は3月19日にワシントンに行って日米首脳会談を行うわけだが、何を持ち出され、何を要求されるか。衆院予算委員会で野党議員からイラン攻撃に対する法的評価を求められると、「今しばらく時間をいただかないと、現段階でその法的な評価ができるというものではないと考えている」と答弁した。
スペインを除く欧州の首脳たちも、正面からトランプのイラン侵攻の国際法違反性を批判できないでいる。3月19日に高市が訪米し、「素晴らしい盟友」トランプと例の満面の笑みで握手すれば、世界はどう見るだろうか。イランはホルムズ海峡を通過する日本のタンカーを攻撃する可能性が出てくる。
先の総選挙の投票日の前日、トランプは「高市内閣を完全かつ全面的に支持する」と言明。「私の支持」が高市首相圧勝の要因だと言い始めているという(3月16日共同)。今度は当然ながら高市に米国のイラン攻撃への全面的な支持を求めて、「恩」を回収しにくるだろう。「高市政権は、すでに足元を見透かされていると言うべきである」(以上、「水島朝穂の東京新聞への直言」2月26日。無料会員登録で3本まで読める)。
重要なことは、安倍晋三政権下で「存立危機事態」の例として挙げられたホルムズ海峡の事態はもっぱら機雷掃海が焦点だったことである(直言「ホルムズ海峡の機雷掃海」)。来週の日米首脳会談では、トランプの要求はそれにとどまらない可能性がある。自衛隊の部隊にホルムズ海峡のみならず、周辺海域のタンカー護衛のためにイージス艦の派遣を求めてきたらどうするか(直言「ホルムズ海峡「存立危機事態」?」)。すでにアフリカ北東部のジブチ共和国には、2011年に恒久的な自衛隊拠点(実質は軍事基地)が設けられ、地位協定まである(直言「戦争可能な正常国家―日米軍事一体化と「統合作戦司令部」」参照)。中東のみならず、アフリカの紛争多発地域をカバーする米アフリカ軍(USAFRICOM)の任務の一部を日本に肩代わりさせていく「MAGA的安全保障戦略」へのコミットを求められたとき、高市はほくほく笑顔で応ずるのか。
25年前、漫画「ドラえもん」に出てくる「ジャイアン」こと剛田武と骨川スネ夫との関係は、どことなく日米関係に似ている気がすると指摘したことがあるが、トランプの米国はもはやジャイアンではない。サナエが「素晴らしい盟友」という相手は一体何に例えたらいいのだろうか。いずれにしても、いい加減に「日米同盟・命」から離陸して、適切な日米関係を構築していくことが求められているのではないか。
《付記》 今日、3月11日は東日本大震災から15年である。このことについて書きたいことはたくさんあるが、とりあえず、10周年の直言「「復興五輪」の終わり方――ドイツとロシアの「3.11」にも触れて」と、7周年の時に書いた直言「東日本大震災7年の福島と憲法」、そして2年前の今日アップした直言「「1.1大震災」から70日――なぜ too late, too little は繰り返されるのか」をお読みいただきたいと思う。